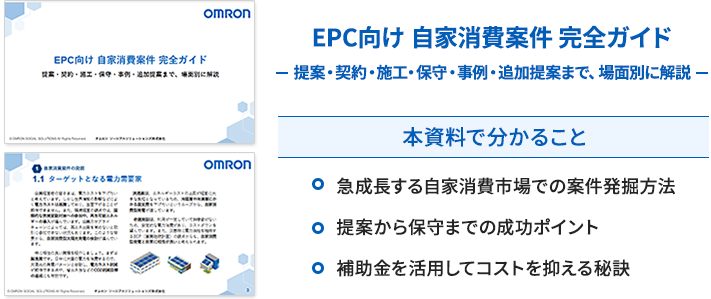お役立ち情報
太陽光発電の自家消費を蓄電池なしでも活用できる工夫とは?導入するメリットも解説

太陽光発電を「自家消費」目的で導入する動きが、住宅をはじめ、工場やオフィスなどの産業施設にまで広がり、注目を集めています。電気代の節約や災害時の電力確保、環境保護など、さまざまなメリットがあるためです。しかし、高額な蓄電池の初期費用がネックとなり、導入をためらうケースも少なくありません。
本記事では、住宅用・産業用の両視点から「蓄電池なしでも太陽光発電を自家消費に活かす方法」をわかりやすく解説します。具体的な運用方法はもちろん、将来的に蓄電池を導入するメリットまでカバーして、導入を検討する際に役立つ情報を幅広くご紹介します。
目次
蓄電池とは?

蓄電池は、電力を貯蔵し、必要に応じて供給できる装置です。家庭やビジネスのエネルギー効率向上に寄与します。電力会社から供給された電力や、太陽光発電などの再生可能エネルギーで発電された電力を蓄電し、停電時や電力需要のピーク時に関わらず、蓄えた電力を利用できるため、安定的な電力供給を実現します。深夜の安価な電力を蓄電し、電気料金が高くなる昼間に使用することで、経済的なメリットも得られます。
再生可能エネルギーの有効活用を促進するだけでなく、非常用電源としての役割も期待されており、社会的に注目を集めています。近年、電気料金の上昇や売電価格の下落を背景に、自家発電した電力を自家消費する住宅やビジネスが増加しつつあり、今後さらなる普及が見込まれます。
太陽光発電に蓄電池の導入をためらう理由

太陽光発電に蓄電池を導入することで、エネルギー利用の効率向上と効果の最大化が実現します。しかし、導入をためらう理由もいくつか存在します。代表的な理由を紹介します。
必要な初期費用
太陽光発電システムに蓄電池を導入する際、初期費用の高さが障壁となるケースが見られます。蓄電池の初期費用は、本体価格に加え、設置費用や電気工事費用も含まれます。さらに、パワーコンディショナの交換費用やハイブリッド型システム採用時の費用増加も考慮する必要があります。これらの費用は、蓄電池の使用による電気代削減を通じて徐々に回収される仕組みです。しかし、初期投資の大きさから、導入に踏み切れないケースが少なくありません。
設置スペースの確保
太陽光発電システムに蓄電池を導入する際、設置スペースの確保は重要な検討事項の一つとなります。蓄電池の設置には一定のスペースが必要です。限られたスペースしかない場合には、よりコンパクトに設計された蓄電池を選択することが賢明です。
小型軽量で設置コストを抑制&電気を有効活用できる蓄電池「住・産共用自家消費対応蓄電システム KPBP-B」はこちらから
また、スペース確保と同時に、設置環境への配慮も欠かせません。屋内設置の蓄電池では、稼働音が生活に影響しないよう設置場所の選定が必要です。一方、屋外設置では直射日光を避け、高温多湿を防ぐ環境づくりが求められます。適切な設置環境が確保できない場合、蓄電池の故障やライフサイクルの短縮といったリスクが生じます。そのため、慎重な判断が重要となります。
蓄電池の寿命
太陽光発電システムへの蓄電池導入を検討する際、蓄電池の寿命が課題の一つとなります。蓄電池は充放電を繰り返すことで使用されますが、経年劣化により蓄電容量が徐々に減少します。長期間の使用で充放電が困難になるケースもあります。そのため、蓄電池の設置には、寿命やその後の交換費用まで事前に考慮する必要があります。
自家消費は蓄電池なしでも可能

太陽光発電の自家消費では、蓄電池を導入しなくても利用が可能です。蓄電池なしの場合、日中に発電した電力をリアルタイムで消費することで電気料金の削減効果が見込まれます。ただし、夜間や天候不良時には発電できないため、電力会社からの電力購入が必要となり、完全な電力自給は難しくなります。また、停電時のバックアップ電源としての活用には注意が必要です。
一方、自家消費しきれない電力は、余剰分として売電することも可能です。さらに、蓄電池を導入しない場合、初期投資を抑えられ、設置工事も簡素化されるため、シンプルな導入を希望する方には適した選択肢と言えます。
蓄電池なしで、自家消費するための工夫

蓄電池なしで自家消費をする場合、自家消費率を向上させるためには工夫が必要です。具体的に4つの工夫を紹介します。蓄電池を導入せずとも、太陽光発電による電力を無駄なく有効活用しましょう。
EPC事業者様に向けた、自家消費型太陽光発電の導入に向けた具体的な提案方法や施工・保守のポイントについては『EPC向け 自家消費案件 完全ガイド』で解説しています。
一定の電力使用量の確保
蓄電池を導入せずに自家消費を実現するには、発電した電力を無駄なく消費することが鍵となります。そのためには、家庭や事務所内で一定量の電力使用を確保する工夫が求められます。例えば産業用の場合には、複数拠点を統合し、従業員の勤務地を集約することで、1事務所あたりの電力消費量を増やすという取り組みも考えられますが、実現難易度は高いかもしれません。
また、発電した電力を有効活用するには、日中に電力消費の多い電化製品を意識的に利用する一方、夜間は省エネ製品を活用し、無駄な電力消費を抑制することが効果的です。これらの工夫により、エネルギーを効率的に活用できるだけでなく、経済的なメリットも得られるでしょう。
電力使用量の調整
電力の使用量やタイミングを適切に管理することが重要です。産業用の場合には、業務用エアコンや照明、業務用冷蔵庫、製造機器など、事業所内の主要設備の運用を意識的に行うことがポイントとなります。特に、太陽光発電で電力が余剰となる時間帯には、これらの機器の稼働を積極的に行うことで、発電した電力を無駄なく活用することができます。このように、太陽光発電で得られたエネルギーを効率的に利用することで、事業所のエネルギーコスト削減と環境負荷低減を同時に実現できるのです。
オール電化の導入
太陽光発電と電化設備を組み合わせることは、発電した電力を効率的に自家消費するうえで非常に有効な方法です。事業所では、調理施設や給湯設備を電化することにより、ガスの使用量を削減し、エネルギーコスト全体の最適化が可能となります。電化された設備を利用することで電力消費量が増加し、その結果、太陽光で発電した電力を無駄なく自家消費できます。
例えば、社員食堂でIHクッキングヒーターを導入したり、電気式の温水器を使用したりすることで、昼間の電力を効率的に活用できます。電化設備の導入は、大規模な設備投資が必要ない場合が多く、既存の運用体制を大きく変更せずに自家消費を効率化できる点が、事業所にとって魅力的です。この方法は、特に昼間の電力消費が多い事業所において、太陽光発電の導入効果を最大化する実践的な工夫として有効です。
電気自動車の活用
電気自動車(EV)は、環境にやさしい乗り物として注目を集めています。走行時に二酸化炭素を排出せず、静音性と力強い走行性能を兼ね備えているため、快適な運転体験が可能です。さらに、EVは非常時の電源としても活用できることから、事業継続計画(BCP)対策としても注目されています。
特に、太陽光発電システムとEVを連携させることで、余剰電力を効率的に活用できる可能性があります。例えば、山梨トヨペット株式会社様は、完全自家消費システムとV2H(Vehicle to Home)を組み合わせることで、購入電力量を大幅に削減しつつ、環境対応を推進しています。詳しくは、以下のリンクから導入事例をご覧いただけます。
山梨トヨペット株式会社様 | 導入事例 | 再生可能エネルギーを創り活用するエネルギーソリューション
それでも推奨する理由|自家消費に蓄電池を導入するメリット

これまでは、蓄電池なしでも自家消費が可能であることを紹介してきましたが、自家消費型太陽光発電のメリットを最大限に引き出すためには、蓄電池の導入が欠かせません。発電した電力を効率的に蓄え、必要な時に使用できるようにすることでメリットを最大化できます。そこで今回は、自家消費における蓄電池導入のメリットについて詳しく解説します。
電気を貯めることができる
発電した電力を貯蔵し、必要な時に自家消費することが可能になります。これにより、夜間や悪天候時でも、電力会社から電気を購入せずに済むというメリットがあります。太陽光発電システム単体では、発電した電力を蓄える機能がないため、発電しない時間帯には電力を利用できません。また、太陽光発電の余剰電力を売電することはできますが、それは自家消費の目的とは異なります。
太陽光発電を効率的に運用し、電力の自家消費を推進するには、蓄電池の併用が最も有効な手段です。蓄電池の導入により、電力の自給自足が実現し、電気代の節減にもつながります。
電力供給が安定化する
太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、一定量の電力供給と自家消費を実現できます。特に、オフィスや工場のような電力需要が変動しやすい場所においては、電力供給の安定性が重要となります。太陽光発電のみでは、天候の変化によって電力供給が不安定になるリスクがあります。
そこで、蓄電池を導入することで、電力需要が少ない時間帯に余剰電力を蓄え、需要が多い時間帯にその電力を放電することが可能になります。これにより、効率的なエネルギー管理を実現できます。日中の日照条件に左右されることなく、柔軟で安定した電力供給が可能となるため、自家消費の利便性と信頼性が向上します。
電気代削減を期待できる
蓄電池を導入すると、日中に発電した電力を自家消費し、余剰分を蓄えることが可能です。これにより、昼間の電力需要が高まる時間帯の使用量を抑え、エネルギーの効率的な運用につながります。また、FIT制度(固定価格買取制度)の終了後は売電価格が低下するため、発電した電力を蓄えて活用する重要性が増します。特に住宅の場合には、より重要です。一般的に日中に家を空けることが多く、夜間や早朝などの太陽光発電量が少ない時間帯に電力を必要とするケースが多いためです。
蓄えた電力を使用することで、その分の電力購入を抑え、電気代の削減が期待できます。加えて、CO₂排出の削減にも貢献し、環境負荷の軽減にもつながります。
停電時、災害時にも安心できる
蓄電池は、電気を蓄える役割を担い、災害や停電時に蓄えた電気を活用することで、非常時の生活を支援します。電力会社からの供給が復旧するまでの間、停電中であっても最低限の生活を維持するための手助けとなるのです。特に事業所においては、停電により生産活動の停止やIT機器・通信インフラの機能不全といったリスクが生じます。蓄電池の導入によってこれらのリスクを軽減することができます。
例えば、冷蔵設備を有する業務用スーパーや医療機関では、停電時においても蓄電池を活用することで、重要な設備の稼働を維持でき、大きな損失を回避できます。このように、蓄電池は災害時や緊急時の事業継続計画(BCP)の一環としても有効であり、導入によって停電リスクに対する安心感を得ることができるのです。
卒FIT後の対策になる
FIT制度が終了し、いわゆる「卒FIT」を迎える太陽光発電システムの所有者にとって、売電価格の大幅な下落は重大な懸念事項となっています。しかし、そのような状況下においても、蓄電池の導入は経済的メリットをもたらす有力な選択肢となり得ます。
蓄電池を設置することで、日中に発電した余剰電力を蓄えておき、夜間や天候不良時など発電量が低下する時間帯に、その蓄電した電力を自家消費に活用できます。これにより、電力会社から高価な電力を購入する必要性が減少し、結果として電気代の負担を大幅に軽減することが可能です。卒FIT後は、発電した電力を安価で売電するよりも、自家消費を増加させ、外部からの購入電力を減らすことがコスト削減の観点からより経済的であると言えます。
環境に貢献できる
太陽光発電は、温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの代表格であり、持続可能なエネルギー利用の観点から注目を集めています。このクリーンな電力を活用することは、地球環境保護に直結します。
特に企業が太陽光発電と蓄電池を導入する場合、環境に配慮した経営姿勢は社会的評価を得られ、SDGs(持続可能な開発目標)を実践している企業として注目されるメリットがあります。さらに、環境経営への積極的な取り組み姿勢は、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の対象として選ばれる可能性を高め、企業価値向上にも寄与します。
蓄電池選びのポイント

太陽光発電と蓄電池を併用することで得られるメリットを理解した後でも、蓄電池選びに悩む方は少なくありません。最適な蓄電池を選定するためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、蓄電池選びの際に考慮すべき6つの具体的なポイントを紹介します。
蓄電容量
蓄電池を選定する際、最も重要な要素の一つが蓄電容量です。蓄電容量とは、蓄電池に充電可能な電力量を指し、kWhという単位で表されます。蓄電容量には多様な選択肢があります。小型のコンパクトタイプでは3kWh程度、標準的なものは5kWh前後、大容量タイプでは10kWh以上のものもあり、用途に応じた選択が可能です。
容量が大きいほど、蓄電池の電力を長時間利用できるため、停電時や悪天候時にも安心感が得られます。ただし、容量の増加に伴い、蓄電池のコストも上昇します。したがって、予算を十分に考慮した上で適切な容量を選定することが肝要です。必要とする電力量を事前に正確に把握し、カタログの記載内容を確認するとともに、不明点があれば施工業者への相談が効果的でしょう。
サイクル数(寿命)
サイクル数も重要な指標の一つです。サイクル数とは、蓄電池の容量が0%から満充電となり、再び0%に戻るまでの一連のプロセスを指します。この値は、蓄電池の寿命を推定する上で目安となる数値です。一般的に、蓄電池のサイクル数は6,000〜12,000の範囲内であることが多いです。ただし、サイクル数だけでなく、蓄電容量とのバランスを考慮することが、耐久性を見極める上で重要となります。
寿命をより正確に算出するには、「蓄電容量×サイクル数=総使用量」という計算式を用います。これが寿命の目安となります。例えば、5kWhの蓄電池でサイクル数が8,000の場合、総使用量は40,000kWhとなります。一方、8kWhの蓄電池でサイクル数が6,000の場合は、総使用量が48,000kWhになります。蓄電池選定においては、サイクル数と蓄電容量のバランスを考慮し、用途に応じた最適な組み合わせを選択しましょう。
充電時間
蓄電池の充電時間は製品ごとに異なるため、選定時の重要な判断基準となります。特に、太陽光発電中に効率的に充電を完了させるには、高速な充電機能を有する蓄電池を選択することが重要です。短時間での充電が可能な製品であれば、日照時間が限られる冬季や悪天候時などの条件下でも、効率的な運用が実現できます。反対に、充電時間が長い製品を選んだ場合、天候や日照時間の変動によって、計画通りに充電が完了しないリスクが高まります。
追加機能
蓄電池には、製品ごとに特有の追加機能が搭載されており、目的や使用状況に応じた選択が可能です。代表的な機能として、「自家消費優先」モード、「売電優先」モード、「停電対策」モードの3つが挙げられます。
「自家消費優先」モードでは、太陽光発電の余剰電力を蓄電池に貯蔵し、発電量が減少した際に蓄電池から電力を供給することができます。これにより、電力会社からの買電量を削減できます。一方、「売電優先」モードでは、余剰電力を売電することで収益化を図り、発電していない時間帯には電力会社からの買電または蓄電池の充電を行います。さらに、「停電対策」モードには、天候情報を活用して蓄電池を満充電にする仕組みが備わっています。これにより、停電に備えることが可能です。
これらの機能を理解した上で、自身のニーズに合致する蓄電池を選択することが賢明な判断といえます。
サイズや形状
サイズや形状、設置場所についても慎重に確認することが必要です。一般的に、蓄電池の容量はサイズに比例するため、設置場所の広さや家庭の電力需要に応じて適切な容量を選ぶ必要があります。設置場所は「屋内専用」「屋外専用」「屋内外兼用」の3種類に分けられます。それぞれの特性や要件を理解した上で選択しましょう。
屋外設置が可能な場合、選択できる製品の種類は広がりますが、防水性や外観が周辺環境と調和するかどうか、さらに設置場所が厳しい環境条件に耐えられるかなどを考慮しなければなりません。一方、屋内設置が求められる場合は、スペースの制約を考慮して薄型・軽量タイプの蓄電池が推奨されます。薄型・軽量モデルを選択すれば、例えば2階のベランダや狭い室内スペースなど、限られた場所でも設置が可能です。
保証内容
一般的な保証期間は10年ですが、15年の製品も存在します。ただし、長期保証はオプションとして有料である場合が多いため、追加費用が発生する可能性がある点に注意が必要です。購入前に保証の条件を詳細にチェックし、適用外となるケースも把握しておくことが重要です。
例えば、蓄電池の改造や、非認定工務店による施工を行った場合、保証が無効になることがあります。保証の適用条件を事前に理解することで、製品購入後のトラブルを未然に防止できます。適切な保証内容を備えた製品を選定することが、長期間の安心利用には不可欠です。
蓄電池に使える補助金制度

蓄電池の導入には、余剰電力の貯蔵や停電時の非常用電源としての活用など、多くのメリットがあります。しかし、高額な初期費用が導入時の大きな障壁となるようです。そのような場合、国や自治体が提供する補助金制度の活用が、コスト抑制に有効な手段となります。
補助金制度の名称や内容、条件は年度ごとに変更されるため、事前に公式サイトや関連機関のページで最新情報を確認することをおすすめします。今回は一例として、「ストレージパリティ達成を目指す補助金制度」を紹介します。この制度は、オンサイトPPA(電力購入契約)方式を用いた太陽光発電設備や蓄電池の導入を支援し、企業や需要家による設備導入を後押ししています。
本制度以外にも、多種多様な補助金制度が存在し、それぞれ異なるメリットや条件があります。企業や個人は、自社や自宅に適した補助金制度を入念に調査し、賢く活用することが重要です。蓄電池導入に関心のある方は、ぜひ各種補助金制度を積極的に活用し、初期コストの負担を軽減しつつ、蓄電池のメリットを享受することをおすすめします。
まとめ
太陽光発電システムの自家消費においては、蓄電池との併用が推奨されています。その理由は、単に節電や環境保護への貢献だけでなく、発電した電力を効率的に活用でき、災害時の備えにもなるからです。日中に発電した電力を蓄え、夜間や消費電力が多い時間帯にも安定的に電力を供給できます。
特に産業用では、工場や商業施設の電力ピークシフトを実現し、BCP(事業継続計画)の一環として非常に有効です。さらに、自家消費型システムの導入は、カーボンニュートラルへの取り組みや企業価値向上にも繋がります。自身の生活スタイルや自社の環境、電力消費量を考慮し、適切な製品選定が重要となります。
最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
「オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社」では、太陽光発電のEPC事業者様向けに、自家消費型太陽光発電案件への提案からはじまり、施工保守、その後の追加提案まで、さまざまな場面毎のノウハウがわかるお役立ち資料を提供しています。