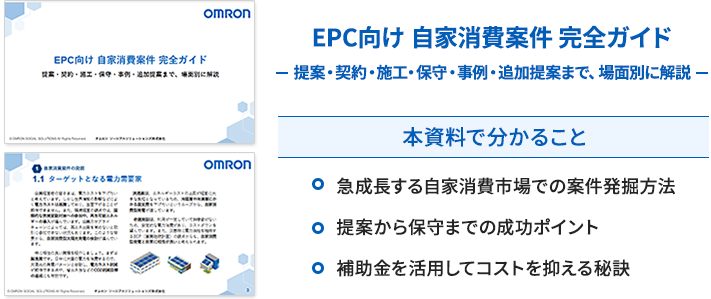お役立ち情報
電気料金高騰時代の解決策!老健福祉施設のコスト削減とBCP強化に役立つ太陽光発電

電気代の高騰、BCP対策の義務化、人手不足による運営の逼迫──。老健福祉施設では、さまざまな課題に直面しながらも、日々の安全・安心な運営が求められています。こうした状況の中、太陽光発電システムは単なる「省エネ設備」ではなく、運営リスクを軽減し、コストを抑える手段として注目されています。本記事では、施設運営者の皆さまに向けて、自家消費型太陽光発電の基本と、導入に向けたポイント、信頼できるパートナーとの連携の重要性を紹介します。
目次
老健福祉施設運営におけるエネルギーの課題
高齢者向け福祉施設や介護施設の運営は今、大きな転換期を迎えています。人件費の上昇や慢性的な人手不足に加え、電気代をはじめとするエネルギーコストの高騰が、施設経営を圧迫する要因として無視できなくなっています。いくつかの課題をみてみましょう。
運営コストの上昇
光熱費は、介護サービスを提供する上で不可欠な費用ですが、近年の電力単価の上昇により、運営費に占める割合が以前にも増して大きくなっています。そのため、現場では「できるだけ無駄を省き、運営コストを抑えたい」という声が高まっています。一方で、利用者の安全や快適性を損なうことはできません。エアコン、照明、給湯、医療機器など、常に安定して稼働させるべき設備が多く、単純にエネルギー消費を削減するだけでは対応しきれないのが実情です。
省エネ対策とエネルギー管理の課題
多くの老健福祉施設では、省エネ型の設備を導入しているものの、施設運営者はエネルギーの専門家ではないため、日常の設定や運用においてエネルギーの使い方が最適化されていないケースも見られます。例えば、電力契約の見直しによってコストを削減できる場合もありますが、契約電力の適正化やピークカットといった電力管理には専門知識が必要です。しかし、そうした対応策があること自体を知らない、または知っていても最適な運用にまで手が回っていないという声も多く上がっています。
BCP対策
近年は災害への備えとして、エネルギーの確保がより重要になっています。国の方針により、2024年4月からは介護施設においてもBCP(事業継続計画)の策定と実行が義務化され、停電時にも一定時間の電力供給を可能にする体制づくりが求められています。しかし、非常用発電機や蓄電池の整備にはコストや手間がかかり、「何から始めてよいかわからない」と感じる施設も多く見られます。
こうした複合的な課題に対し、「今ある設備の見直し」だけでは限界があるというのが現場の実感ではないでしょうか。だからこそ、近年注目されているのが「自家消費型太陽光発電」の活用です。電気を自らつくり、その場で消費するという仕組みは、コスト削減にもBCP対策にもつながり、施設運営のリスクを分散する有効な手段として期待されています。
老健福祉施設における自家消費型太陽光発電のメリット
自家消費型太陽光発電システムの導入が、老健福祉施設にとってどのような意味を持ち、どんなメリットがあるのでしょうか。電気料金の削減といった効果は想像しやすいかもしれませんが、それだけではありません。施設の安全性や信頼性の向上に加え、地域や社会に対する姿勢のアピールといった、多面的な価値をもたらします。ここでは、主な3つのメリットについて紹介します。
1. エネルギーコストの削減
最も分かりやすいメリットは、電気料金の削減です。太陽光発電によって日中の電力消費の一部をまかなうことで、電力会社からの購入電力量を減らすことができます。特に昼間の電力使用量が多い老健福祉施設にとっては、自家消費による経済効果が大きくなります。
また、今後も続くと見込まれる電気料金の上昇リスクに対して、発電した電力を自ら使うことで、長期的視点で安定した運営にもつながります。さらに、空調や給湯設備などの使用タイミングを調整することで、電力消費のピークを抑え、契約電力の見直しによるコスト削減効果も期待できます。
2. BCP対策としての活用
太陽光発電は、災害時の非常用電源としても役立ちます。地震や台風などによる停電時でも、日中は太陽光で最低限の電力を確保できるため、入居者の安全・安心に貢献します。蓄電池を組み合わせることで、夜間の電力供給も可能となり、照明や通信機器、非常用冷暖房などの継続運用にも備えることができます。
先に説明した通り、2024年4月からは、介護施設におけるBCP(事業継続計画)の策定と実行が義務化されており、災害対応力の強化は、今後の施設運営において避けて通れない課題です。太陽光発電システムと蓄電池を活用した電力の自立供給は、その対策の一環として有効です。
3. 環境貢献とブランディング
自家消費型太陽光発電は、再生可能エネルギーによってCO₂排出量を削減できる、環境にやさしい取り組みでもあります。昨今は、自治体や入居者のご家族など、周囲からの「持続可能な運営」への関心が高まっており、施設としての社会的責任(CSR)やSDGsへの対応を示す上でも、有効な手段といえます。
さらに、「環境に配慮し、災害にも備えた安心・安全な施設運営」を明確に打ち出すことは、ブランディングの面でも大きな価値があります。こうした姿勢は、施設の信頼性や地域からの評価を高めるだけでなく、入居促進や人材採用にもプラスの影響を与える可能性があります。
老健福祉施設が知るべき自家消費導入のポイント

自家消費型太陽光発電は、適切に計画・運用することで、20年以上にわたって安定した効果をもたらすエネルギー対策です。導入時には、施設の規模や運営状況、電力の使用パターンを踏まえ、システム容量や運用方法を最適に設計することが成功のカギとなります。
ここでは、自家消費型太陽光発電を導入するにあたり、老健福祉施設が押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
1. 施設のエネルギー使用状況を分析する
まず必要なのは、自施設で「いつ・どれくらい」電気を使っているのかを把握することです。特に重要なのは、電力を多く使用している時間帯(ピーク時間)や、空調・給湯・厨房設備などの用途ごとの消費傾向を知ることです。
分析の第一歩としては、施設に設置されているスマートメーターの計測データを活用する方法があります。多くの施設ではすでにスマートメーターが導入されており、30分単位で記録された電力使用データが取得可能です。これらのデータは、電力会社や契約している小売電気事業者に依頼すれば、過去数カ月分を提供してもらえる場合があります。
さらに詳しく分析したい場合は、エネルギーの使用状況を可視化する簡易診断サービスや、分電盤ごとの電力量を計測するエネルギーマネジメント機器を活用する方法もあります。こうしたツールや情報にアクセスするために、省エネ設備や太陽光発電の施工会社(以下、施工会社)に相談するのも一つの方法です。
使用状況をもとに、太陽光発電でどの程度の電力を補えるのか、どの時間帯に有効かを見極めることができ、施設にとって適切なシステム容量の検討にもつながります。
2. 受電契約の違いを理解する
太陽光発電の導入を考える上で、施設が現在どのような電気契約(受電契約)をしているかを知ることはとても重要です。
施設の電気契約は大きく分けて「低圧契約」と「高圧契約」の2種類があります。低圧契約は、比較的小規模な施設が対象で、導入できる太陽光設備の規模もコンパクトなものになります。初期費用を抑えやすく、小さく始めたい施設に向いています。
一方、高圧契約は、利用者数が多い施設や、設備が多く電力をたくさん使うような大規模施設が対象です。太陽光発電設備もやや大きなものが導入されることが多く、より多くの電気を自家消費できる分、コスト削減効果も高くなります。こうした契約の種類によって、導入できる設備や設計の考え方が変わってきます。どちらに該当するか分からない場合や、どう設計すべきか判断がつかない場合は、施工会社に相談することで、無理のない導入計画を立てられます。
3. 導入コストと投資回収期間を把握する
太陽光発電の導入には一定の初期費用がかかりますが、長期的には運営コストの削減につながるため、投資としての側面も見逃せません。例えば、50〜100kWクラスのシステムを導入する場合、費用の目安はおよそ2,000万円前後となります。
多くの太陽光パネルには「20年間で発電性能80%以上を維持する」といった長期保証が付いており、安定した発電が20年にわたって期待できます。そのため、導入から約10年で投資を回収できれば、残りの10年間は電気料金の削減効果がそのまま運営の利益につながるという考え方が一般的です。
さらに、自治体や国の補助金制度を活用すれば、初期費用を抑え、回収期間をより短くできる可能性もあります。導入前には、こうした制度の有無や内容を事前に確認することが大切です。
4. 導入後のエネルギー管理も重要
太陽光発電は「設置して終わり」ではありません。施設内の他の設備と連携しながら、電力の使い方を見直すことで、さらに効果的な運用が可能になります。例を挙げると、発電量に合わせてボイラーや空調設備の運転時間を調整し、契約電力を見直すことで、さらなるコスト削減につながる可能性もあります。
導入前に押さえておきたい費用・回収のポイント
老健福祉施設において太陽光発電システムの導入を検討する際には、費用や回収の見通しを把握することが欠かせません。ここでは、「導入コスト」「回収期間」「補助金活用」「資金調達」といった観点から、導入前に押さえておきたい4つのポイントを紹介します。
1. 導入コストの目安
50〜100kWクラスのシステムを導入する場合の初期費用が約2,000万円前後と説明しましたが、もう少し詳しくみていきましょう。
50~100kWクラスの設備は、老健福祉施設の屋根や敷地の一部に設置できる中規模程度のシステムです。年間の発電量はおおよそ5万〜10万kWh程度とされており、昼間の電力使用量が多い施設においては、日中の消費電力の一部から半分程度をまかなえる規模といえます。
必要な設置面積は、目安として300〜600㎡(およそ100〜200坪)程度の屋根スペースが必要とされることが多く、施設の屋根形状や方位によっても変動します。
2. 投資回収期間
太陽光発電システムの投資回収期間は、一般的に約10年程度を目安として計画されることが多く、これは主に電気料金の削減効果を積み重ねて初期費用を回収していくという考え方に基づいています。
電気料金の単価は契約種別や地域によって異なりますが、電気料金単価を25円/kWhと想定し、年間10万kWhを自家消費した場合、削減できる電気代は年間250万円となります。導入費用が2,000万円だとすると、約8年で初期投資の回収が可能という計算になります。なお、借り入れの金利やリースなどに関する経費は省略しております。あくまで概算の参考値としてご覧ください。
- 【計算式】年間削減額(万円)= 年間発電量(kWh)× 電気単価(円/kWh)÷ 10000
- 【例】100,000kWh × 25円 ÷ 10000 = 年間削減額 250万円
- → 2,000万円 ÷ 250万円 = 回収年数 約8年
前述の通り、太陽光パネルは20年程度の長期利用が見込まれており、導入から10年ほどで投資を回収できれば、その後の10年間は削減効果がそのまま施設運営の利益に直結します。もちろん、安定した運用を維持するためのメンテナンス費用は発生しますが、電気代の大幅な削減によって一定の利益を確保できるでしょう。
なお、補助金を活用して初期費用を抑えれば、設備を増強したり回収期間を短くしたりすることも可能です。導入時には、こうしたコストと効果のバランスを事前に試算することが、現実的な判断のために重要です。詳しい計画については、施工会社に相談するのが確実です。
3. 補助金や助成金の活用
国や自治体は、省エネや再生可能エネルギーの導入を促進するため、さまざまな補助金や助成金を提供しています。
例えば、医療・介護・社会福祉法人などが設置する太陽光発電や蓄電池、LED照明、空調設備などに対して、上限数千万円から最大1億円規模の補助金が利用可能となるケースもあります。これらの制度を活用すれば、初期投資の負担を大幅に軽減することが可能です。補助金の対象範囲や申請条件、スケジュールは年度や自治体によって異なるため、最新の情報を確認することが導入成功の秘訣となります。
オムロン ソーシアルソリューションズでは、太陽光発電や蓄電池の導入を検討している事業者向けに、国や自治体の補助金情報をまとめたページも提供しています。施設ごとの状況に合わせて、どの制度が適用可能かを確認する際に参考にしてください。
4. 金融機関からの資金支援
地方銀行をはじめとする金融機関は、再生可能エネルギー事業への取り組みを強化しており、太陽光発電導入に関する融資やリースなどの資金支援プランを提供しています。特に、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資への関心が高まる中、ポジティブ・インパクト・ファイナンス(PIF)と呼ばれる融資手法が注目されています。
PIFとは、企業活動が環境・社会・経済に与える影響を包括的に分析し、プラスの貢献(ポジティブインパクト)の向上と、マイナスの影響(ネガティブインパクト)の緩和・低減に向けて、KPI(重要業績評価指標)を設定し、金融機関がモニタリングしながら支援する融資手法です。
グリーンエネルギーに関連した融資プランを活用することで、自己資金の負担を軽減しつつ、太陽光発電の導入を進めることが可能となります。具体的な支援内容や条件は、各金融機関によって異なるため、取引のある金融機関に問い合わせてみることをおすすめします。
太陽光発電導入のステップと相談先

自家消費型太陽光発電の導入は、複雑に見えるかもしれませんが、信頼できる相談先を確保し、段階的に検討を進めれば、無理のない導入が可能です。ここでは、検討開始から導入後の運用まで、実際の進め方をイメージできるよう、基本的なステップを紹介します。
ステップ1. 「相談先」の確保
まずは、施工会社や自治体、金融機関などに相談するところからスタートします。施設ごとの事情や目的に応じて、どのような進め方が適しているかを一緒に検討することが大切です。特に施工会社は、提案から施工、運用支援までを一貫して担うパートナーとなるため、複数社に相談し、見積もりや提案内容を比較しながら慎重に選定していくことが望まれます。
ステップ2. 施設のエネルギー使用状況の確認と提案依頼
施工会社に依頼をすることで、スマートメーターのデータなどをもとに、施設の電力使用パターンやピーク電力、設備の稼働状況などを分析してもらうことができます。その上で、適切な設備容量や構成案、試算資料などの提案を受けることができます。この段階で、導入によるコスト削減効果や投資回収期間の見込みが明確になります。
ステップ3. 補助金や融資の可能性を確認
提案内容をもとに、国や自治体の補助金、あるいは金融機関による資金支援の対象になるかどうかを確認します。必要に応じて、施工会社から補助金申請の支援を受けたり、地元の銀行に融資を相談したりすることで、初期費用の軽減や回収期間の短縮が見込めます。
ステップ4. 施工会社の選定と契約、現地調査へ
複数の提案を比較検討した上で、信頼できる施工会社を選定します。正式な契約後には現地調査や設計の詳細化が行われ、補助金の本申請もこのタイミングで進めるのが一般的です。
ステップ5. 設計・施工・運用開始へ
設計が完了したら、工事が開始されます。施工完了後は、試運転・系統連系の手続きを経て運用開始となります。運用後は、日常的な発電状況のモニタリングや、設備の点検・保守などのアフターサポートも重要です。
まとめ:まずは現状把握から始めましょう
電気料金の高騰やBCP対策、省エネ対応といった課題に直面する老健福祉施設にとって、自家消費型太陽光発電は、運営の安定化とリスク分散を同時に実現できる有効な手段です。導入にあたっては、単に設備を設置するだけでなく、エネルギー使用の見直しや設備の最適な運用計画を立てることが重要です。補助金や金融支援なども活用しながら、施工会社と連携し、施設に合った無理のない導入を進めていきましょう。
まずは、自施設の電力使用状況を把握し、どのような導入が可能かを専門家に相談してみることが、最初の一歩です。例えば電力会社に電気の使用状況データを問い合わせたり、施工会社へ相談してみたりするのも有効です。
なお、オムロン ソーシアルソリューションズでは、産業用自家消費太陽光発電システムに関する情報を発信する特設サイトを用意しています。電力需要家様向けの情報も提供していますので、参照ください。
https://socialsolution.omron.com/jp/ja/products_service/energy/self-consumption/