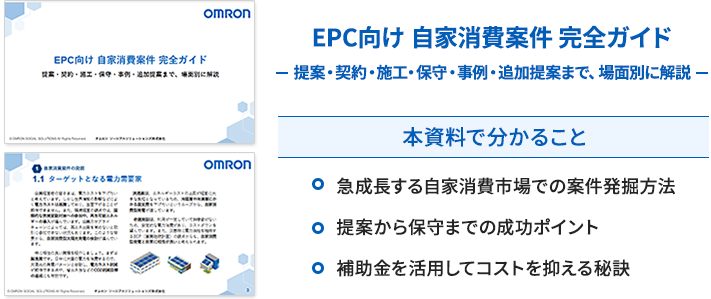お役立ち情報
太陽光発電を売電から自家消費へ切り替えるメリットとは?注意点や背景まで詳しく解説

太陽光発電の導入は、住宅用と産業用で事情が大きく異なるものの、昨今はどちらでも「売電よりも自家消費のほうが経済的メリットを得られるケース」が増えています。FIT制度(固定価格買取制度)による買取価格の下落と電気料金の上昇によるものです。本記事では、住宅用・産業用の両面から自家消費のメリットについて解説するとともに、自家消費を最大化するためのノウハウをお伝えします。
目次
太陽光発電の自家消費とは?

自家消費とは、太陽光発電で自ら発電した電気を、自宅や自社で直接消費することを指します。これにより、電力料金の削減や費用の安定化、さらには環境保護への貢献が期待できます。一方、売電とは自分では使い切れない余剰電力を電力会社に販売し、収益を得る方法です。
自家消費の方法には、発電した電力をすべて自分で使用する「完全自家消費型」と、一部を使用した後に余った電力を売電する「余剰売電型」の2種類があります。それぞれの方法について、より詳しく解説していきます。
完全自家消費型
「完全自家消費型」とは、太陽光発電で発電した電力をすべて施設内で消費し、売電を行わない方式を指します。この方式は、特に昼間の電力消費が多い工場やオフィスビルなどの産業用施設に適しており、発電した電力を効率的に活用することができます。自家消費を行うことで、外部からの電力購入量を減らすことができ、電気代削減という大きなメリットがあります。
さらに、消費量が少ない場合でも、蓄電池を併用することで余剰電力を無駄なく活用でき、持続可能性を高めることが可能です。完全自家消費型は、経済面と環境面の両方でメリットが大きい太陽光発電の活用方法であるといえます。
余剰売電型
一部の電力を自家消費し、余剰分を電力会社に売る仕組みが「余剰売電」と呼ばれます。この方式では、FIT制度を利用する場合でも、一定割合の電力を自家消費する必要があります。割合は年度や区分で異なり、詳細な要件に基づき運用されます。この制度を利用することで、電力消費が一定の施設(例えば、介護施設や業務用スーパーなど)でも、電気代を削減しながら効率的な電力運用が可能です。
売電から自家消費への切り替えが増えている背景

近年、太陽光発電における余剰電力の扱いに変化が見られます。従来は電力会社への売電が主流でしたが、自家消費を選択する企業・家庭が増加しています。この背景には何があるのでしょうか。
市場の変化を踏まえ、EPC事業者様が自家消費型太陽光発電の導入を支援するために求められる具体的な提案方法や施工・保守のポイントについては、『EPC向け 自家消費案件 完全ガイド』で解説しています。
グリッドパリティの実現
グリッドパリティとは、再生可能エネルギーによる発電コストが、従来型電力の供給コストと同等、またはそれ以下になる状態を指します。具体的には、太陽光発電の電力単価が、電力会社から供給される電力料金を下回ることを意味します。
例えば、2024年の住宅用太陽光発電(10kW未満)のFIT制度による売電価格は16円/kWh、産業用太陽光発電(10kW以上50kW未満の屋根設置)では12円/kWhでした。一方、一般家庭向け電力料金の目安は約31円/kWh(全国家庭電気製品公正取引協議会が「新電力料金目安単価」として、令和4年7月22日に改定)で、その差額は15円/kWhにもなります。
出典元)よくある質問 Q&A
この差額により、自家発電した電気を自ら使用することで電気代の節約が可能になります。産業用施設においても同様の節約効果が期待できます。近年、多くの地域でグリッドパリティが実現し、これに伴い太陽光発電の売電から自家消費への切り替えが増加しています。再生可能エネルギーの経済性向上により、環境に優しい電力の活用が加速しているのです。
ストレージパリティの達成
ストレージパリティとは、蓄電池の導入によって経済的メリットが得られる状態を指します。具体的には、「グリッドパリティ」の概念を蓄電池に応用したものです。蓄電池の設置により電力の需要値(デマンド値)を下げることで、基本料金の削減が可能となり、電気料金全体の抑制が期待できます。蓄電池導入による削減額が、初期費用や維持費を上回った時点で、ストレージパリティが成立します。
また、政府は蓄電池普及推進のため、補助金を用意しています。太陽光発電への補助金適用の条件として「蓄電池の設置」が必須とされるケースが増えています。補助金が利用可能な現在は、蓄電池の導入と太陽光発電電力の自家消費を検討するまたとない機会だと言えるでしょう。
太陽光発電の売電価格は下がり続けるのか?

太陽光発電の売電価格が今後どのように推移するのか、詳しく解説します。
FIT制度の売電価格の傾向
太陽光発電の売電価格は、これまで導入コストの低下や国民負担を抑制する観点から、徐々に下落していました。しかし、2025年10月以降は、設置容量が50kW未満の屋根設置型に限りますが、売電価格が大幅に引き上げられる予定です。(2025年3月現在)
住宅用(10kW未満)の屋根設置型では、最初の4年間は24円/kWh(24年度比+50%増)、残り6年間は8.3円/kWhとする分割型が導入されます。産業用(10kW以上50kW未満)の屋根設置型では、最初の5年間の買取価格は19円/kWh(24年度比+60%増)、残り15年間は8.3円/kWhとなります。
価格の引き上げにより初期投資を早期に回収できるようにすることで、住宅用では「新築物件における2030年までの太陽光パネル搭載率60%」、産業用では「融資の円滑化」を目的としています。ただし、これらはあくまで一時的な施策であり、今後さらに売電価格が上がる見通しは低いと考えられています。
太陽光発電の導入が進み、設備の量産体制が整備されるとともに、技術開発も進展しました。その結果、太陽光発電関連製品の価格は大幅に下落しています。加えて、電力買取の費用の一部が再エネ賦課金として消費者の負担となっているため、社会全体の負担増を抑制する必要があることから、売電価格の恒常的な引き上げは難しい状況にあります。長期的には、再び下落傾向に戻るか、現状維持に留まる可能性が高いでしょう。その前提で計画を立てることが重要です。
卒FIT向けの売電価格の傾向
太陽光発電の卒FIT向け売電価格は、現状の水準で据え置かれる公算が大きいとされています。しかし、将来の動向には注意が必要です。太陽光発電の普及により、発電効率の向上や新技術の進展が見込まれており、これらが売電価格に影響を及ぼす可能性があるためです。
一方、太陽光発電の設置数の増加に伴い、電力会社が負担する買取コストも増大することが予想されます。その結果、卒FITの売電価格はFIT制度で保証されていた価格を下回る水準に設定されており、多くの発電事業者にとって厳しい状況が続いています。
また、需要量が供給量を大幅に上回らない限り、売電価格が大きく引き上げられる可能性は低いとみられています。総じて、卒FIT後の売電価格は安定しつつも低水準で推移する傾向にあり、自家消費への切り替えを検討する動きを加速させる要因となっているのです。
太陽光発電事業者は、卒FIT後の売電価格の動向を注視しながら、収益性の確保に向けた対策を講じることが求められるでしょう。
売電から自家消費へ切り替えるには?

FIT制度の適用期間が終了した後、売電から自家消費型へ切り替えるためには、一定の手続きが必要となります。本記事では、その方法について2つの視点から解説します。
電力会社へ申請する
太陽光発電システムを導入し、余剰電力の売電から自家消費へ切り替える際には、電力会社への契約変更申請が不可欠です。申請を行わずに自家消費を増やすことは可能ですが、売電収入の減少により経済的メリットが減少する可能性があります。特に電気代の削減を主目的とする場合は、契約変更申請を必ず行うことが重要です。
契約変更の具体的な方法や手続きは、電力会社によって異なります。そのため、詳細については各社の公式ホームページを確認するか、太陽光発電システムの導入に精通した専門業者に相談することをお勧めします。
必要な設備を導入する
太陽光発電において売電から自家消費へ切り替える際、適切な設備導入が不可欠です。特に重要なのが、逆潮流防止のためのRPR(逆電力継電器)と、発電量管理のための制御装置の設置です。逆潮流とは、発電した電力が電力会社側へ流れ込む現象を指します。自家消費への切り替えでは、この現象の防止が大切となります。自家消費量が少ない場合、発電量が余剰となり、逆潮流が発生する可能性があります。そのため、制御装置を用いて発電量を適切に調整することが求められます。
これらの設備導入により、自家消費への切り替えがスムーズに進みます。また、余剰電力発生のリスクを最小限に抑えることができます。
売電から自家消費へ切り替えるメリット

売電から自家消費へ切り替えることで、電気料金の削減や災害時の電力確保などのメリットが得られます。ここでは、売電から自家消費へ切り替えるメリットについて詳しく解説します。
電気料金の節約に繋がる
自家消費型太陽光発電は、電気代削減に高い効果を発揮し、効率的なコスト削減を実現します。発電した電力をすべて自家消費することで、電力会社からの購入量を大幅に減らせます。2022年以降、国際情勢の変化や円安の影響で電気代が高騰し、多くの家庭や企業経営に大きな負担となっています。FIT制度の買取単価が固定されている売電型太陽光発電では、電気代の上昇分を十分に補えないケースもあります。
一方、自家消費型太陽光発電は市場の電気価格変動の影響を受けにくく、電気代高騰時でも固定費負担を抑制できます。そのため、電気料金対策としては売電型より自家消費型への切り替えが有効となっています。自家消費型太陽光発電は環境面だけでなく経済面でも大きなメリットがあり、今後さらに注目される技術でしょう。電気代高騰に悩む家庭や企業にとって、自家消費型太陽光発電への切り替えは賢明な選択肢の一つといえます。
売電価格の変動に影響を受けなくなる
自家消費型太陽光発電に切り替えることで、売電価格の変動リスクから解放されます。卒FIT後の電力会社プランの多くは、従来の固定買取価格を下回る水準に設定されており、売電型太陽光発電では十分な収入確保が困難な状況です。加えて、固定買取価格は年々下落傾向にあり、売電主体の事業環境は厳しさを増しています。
一方、自家消費型太陽光発電は売電収入に依存しないモデルで運用されるため、価格変動の影響を受けません。そのため、自家消費型太陽光発電は安定運用が期待できる新たな事業形態と言えるでしょう。
BCP対策になる
自家消費型太陽光発電は、BCP(事業継続計画)対策として非常に有効であり、自然災害や停電への備えとして重要な役割を果たします。非常用電源として機能し、停電時でも住宅や企業における重要な機能の維持が可能となります。住宅では、照明、冷蔵庫、電子レンジなどの基本的な家電の稼働が可能であり、日常生活の維持に貢献します。
一方、企業においては、パソコンや生産設備の稼働を通じて、データ保護や事業活動の迅速な再開を図ることができます。さらに、非常時にWi-Fiを利用することで、従業員の安否確認や応急対応の連絡手段としても活用でき、コミュニケーションインフラの維持に寄与します。自家消費型太陽光発電は、住宅や企業におけるBCP対策の要として、重要性が高まっています。
脱炭素経営の推進に繋がる
企業が太陽光発電を自家消費へと切り替えることは、脱炭素経営の推進に大きく貢献します。自家消費型太陽光発電の導入は、企業の環境に対する積極的な姿勢を具体的に示す手段となり、企業イメージの向上につながるでしょう。
世界的に脱炭素化やカーボンニュートラルへの取り組みが加速する中、企業にもこれらの実施が強く求められています。自家消費型太陽光発電の導入は、こうした社会的要請に応える効果的な手段の一つと言えます。さらに、自家消費型太陽光発電の導入により、取引先との信頼関係の強化が期待できます。環境に配慮した企業として評価されることで、新規取引先の獲得やビジネスチャンスの拡大につながる可能性があり、企業の競争力向上にも寄与するでしょう。
自家消費を最大限活用する方法

自家消費を最大限に活用する方法について詳しく解説します。
蓄電池を活用する
太陽光発電と蓄電池を組み合わせることで、発電量の不安定さを補い、安定的な電力供給が実現します。例えば、夜間や悪天候時でも蓄電池に蓄えた電力を自家消費できるため、エネルギー効率の向上につながります。
さらに、この太陽光発電と蓄電池の組み合わせは、災害時の防災対策としても大きな効果を発揮します。停電時でも、家庭や施設に電力を供給することが可能となります。
蓄熱機器に供給する
太陽光発電の電力を蓄熱機器の稼働に利用することは、自家消費を効率的に実現する上で有効な手段です。例えば、エコキュートを日中に稼働させれば、太陽光発電の電力を活用しつつ、電気代を削減できるだけでなく、お湯の沸かし直し回数が減るため、省エネルギー効果も期待できます。
また、電気自動車(EV)への充電も、自家消費率の向上に役立ちます。EVは蓄電池としての機能も備えており、家庭やオフィスへの電力供給が可能なため、非常用電源としての役割も果たしてくれます。
売電から自家消費へ切り替える際の注意点

太陽光発電の売電から自家消費への切り替えには、多くのメリットがある一方で、いくつかの注意点も存在します。自家消費への移行を検討する際は、これから紹介する注意点も十分に理解した上で、専門家のアドバイスを参考にしながら計画的に進めていきましょう。
制御機器の導入が必要
売電から自家消費へ切り替える際には、専用の制御機器の導入と工事が不可欠です。この制御機器は、家庭や施設の消費電力量に応じて発電量を自動調整することで、効率的な運用を実現します。これにより、無駄な発電を抑制し、設備の寿命延長も期待できます。
一方、制御機器を設置せずに運用すると、逆潮流防止機能が頻繁に作動し、発電が繰り返し停止する可能性があります。このような頻繁な停止は、機器の部品劣化を早めるリスクがあるため、注意が必要です。
蓄電池の維持費用が必要
蓄電池を併用することで、発電量が少ない夜間などでも電気を自家消費でき、電力運用の効率化が図れます。しかし、蓄電池の初期費用や維持費には注意が必要です。
特に故障や寿命による交換時には、100万円前後の高額な出費となるケースもあります。そのため、長期的な視点で維持費用を見積もり、初期費用と合わせた総合的なコスト計画を立てることが重要です。また、販売店や施工会社との入念な打ち合わせを通じて、機器の性能や保証内容を事前に十分に理解しておくことも欠かせません。
売電時とは異なる収支計画が求められる
売電型とは異なる収支計画の構造を理解することが重要です。売電型では、発電した電力を売却して得られる収入が主な収益源となり、設備投資やメンテナンス費用を差し引いた利益を得ます。一方、自家消費型では、発電した電力を自ら使用することで電気代を削減し、そのコスト削減効果分が利益となります。このため、自家消費型の収益は目に見えにくい特徴があります。
つまり、電力を売るか使うかという根本的な違いが、各方式の収益構造に直接影響を与えています。したがって、自家消費型の導入を検討する際は、両方式のメリット・デメリットを比較し、自家消費型を導入する目的や期待する成果を明確にしましょう。
売電から自家消費へ切り替えない場合の選択肢

太陽光発電のFIT制度の買取期間終了後は、売電以外にも様々な選択肢が検討可能となります。本記事では自家消費への切り替えを推奨していますが、仮に自家消費へ切り替えない場合でも、その後の運用方法は多岐にわたります。自身の状況に応じて適切な方法を選択することが重要です。ここでは3つの選択肢を紹介します。
売電を継続する
太陽光発電による売電の継続は選択肢の一つとして考えられます。ただし、FIT(固定価格買取制度)における買取価格の低下や制度変更の可能性があるため、売電先の選定には慎重な検討が必要です。複数の電力会社の条件を比較し、長期的な視点で有利な売電先を選択することが重要となります。
同じ売電先との契約を継続
現在の売電先との契約に満足しており、変更する明確な理由がない場合は、同一の売電先と契約を継続するという選択肢もあります。新規の売電先を探すためには手続きが複雑で、他社との比較に時間を割くことが難しい場合においても、現状維持が効果的な方法だと言えるでしょう。
ただし、現在の契約を継続したとしても、より良い条件の売電先が後から見つかった場合は、その時点で契約を変更することができます。現時点では情報収集を進めながら、既存の契約を維持し、状況を見極めることも重要です。
売電先を新たに切り替える
売電先を切り替える際は、複数の電力会社の買取価格やサービス内容を比較することが重要です。特に高い買取価格を提示する電力会社を選択することで、収益性の向上が期待できます。ただし、価格のみならず、馴染みのある事業者や自宅のエネルギー利用状況に適したプランを提供している会社も選択肢に含めるべきでしょう。
売電先の変更手続きは比較的簡便で、書類の提出や電話連絡で完了することが多いです。手続きの負担は少ないと言えます。
タイミングを見計らい、切り替える
FIT制度の終了後、即座に自家消費へ切り替える必要はありません。自由契約に基づく売電を継続しつつ、電力の買取価格や需要を確認しながら判断することも選択肢の一つです。また、蓄電池の価格動向や新商品情報を随時チェックして、自家消費を導入する費用対効果を見極めるのも良いでしょう。
将来の電力需要や価格変動を見通した上で、最適なタイミングを見計らい、計画的に自家消費への移行を検討することも賢明と言えます。
太陽光発電から撤退する
太陽光発電設備の維持費が経済的メリットを上回る場合、選択肢の一つとして「撤去」を考えることができます。ただし、撤去には一定の費用が発生します。住宅用の場合、撤去費用は15万円前後とされています。一方、産業用の場合は初期費用の約5%程度に及ぶこともあります。
しかし、産業用では廃棄費用の積み立てが義務化されており、その積み立て金を撤去費用に充てることが可能です。太陽光発電設備の維持費と撤去費用、経済的メリットを総合的に判断し、太陽光発電から撤退するかどうかを決定する必要があります。
自家消費型太陽光発電で活用できる補助金制度

自家消費型太陽光発電の導入には、国や地方自治体が提供する補助金や支援制度を活用できます。多くの補助金制度があります。一例を紹介します。国の制度としては、「中小企業経営強化税制」があり、完全自家消費型の太陽光発電を導入した場合に、即時償却や税額控除が適用されます。
地方自治体でも独自の支援制度を展開しています。例えば神奈川県では、「消費型再生可能エネルギー導入費補助事業」を実施しています。法人や個人事業主を対象に、太陽光発電設備や蓄電システムの導入にかかる経費の一部を補助しています。このように、自家消費型太陽光発電の導入を検討する際は、国や地方自治体の補助金や支援制度を有効活用することで、初期投資の負担を軽減できます。
まとめ
太陽光発電の運用方法には、売電と自家消費の2つがありますが、どちらが有利かは一概には言えません。しかしながら近年では、多くの地域で再生可能エネルギーの発電コストが従来型の電力供給コストと同等、またはそれ以下になる状況が増えており、売電から自家消費への切り替えが進んでいます。
自家消費には、電力市場の価格変動に左右されないことや、電気代の削減、非常用電源の確保といった多くのメリットがあります。特に産業用施設においては、BCP(事業継続計画)対策として非常時の電力確保がより重要となるだけでなく、脱炭素経営の推進に貢献でき、企業価値の向上にも繋がります。
ただし、自家消費への切り替えには、蓄電池の導入や初期コストについても計算に入れた上で、正しく計画する必要があります。FIT制度(固定価格買取制度)の終了後には、状況を見極めるためにまずは売電を継続し、タイミングを見計らって自家消費に切り替えるという現実的な選択肢もあります。家庭や企業における電力の使用状況や、太陽光パネルの設置状況まで含めて総合的に判断しましょう。
最後までお読みいただき誠にありがとうございます。
「オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社」では、太陽光発電のEPC事業者様向けに、自家消費型太陽光発電案件への提案からはじまり、施工保守、その後の追加提案まで、さまざまな場面毎のノウハウがわかるお役立ち資料を提供しています。