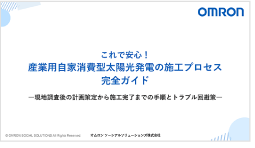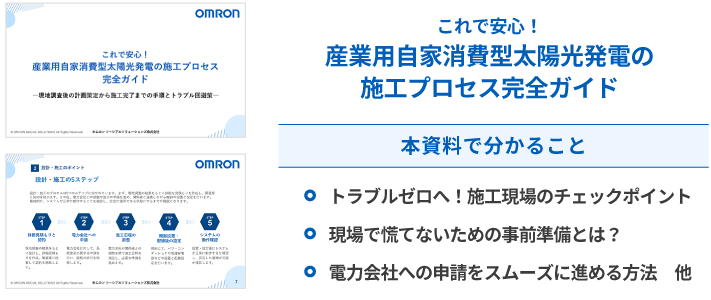お役立ち情報
電気設備の安全点検「電気保安点検」とは?具体的な内容から、事前対策や課題まで解説

電気設備の安全性を確保するためには、定期的な点検が必要不可欠です。特に、法律で義務付けられている「電気保安点検」は、点検における重要な役割を担っています。この点検は主に月次点検と年次点検に分けられます。年次点検では電気工作物を停電状態にして入念にチェックするため、事業運営への影響も少なくありません。そのため、事前の綿密な準備と対策が求められます。
電気保安点検を正しく理解して、適切な体制を整えることが安全な設備運用の鍵となります。本記事では、電気保安点検の具体的な内容から、点検における課題や解決策まで、幅広い情報を提供します。電気保安点検の重要性を再認識し、事業場の安全性向上につなげましょう。
目次
電気設備の安全点検「電気保安点検」とは?

電気保安点検とは、電気事業法に基づき、受電設備や配線などの電気設備を定期的に点検する法的義務のある業務です。この点検は義務化されており、電気工作物(高圧受電)の所有者や使用者自らが依頼しなければなりません。点検には「法定点検」と「自主点検」の2種類があります。法定点検は法律で定められた停電を伴う試験や点検を指し、保安規定に従って実施されます。一方、自主点検は事業者が独自に設定した保安規定に沿って行う点検で、自家用や事業用の電気設備が対象となることが多いです。
点検の対象となる電気設備には、発電所や変電所、オフィス、住宅の受電設備などが含まれます。点検を依頼する際には、担当の保安業務従事者に連絡を取り、点検の種類や頻度を事前に確認し、必要な準備を整える必要があります。電気保安点検は、電気設備の安全性を確保し、事故や故障を未然に防ぐ上で重要な役割を果たしています。
定期的な点検により、電気設備の異常や劣化を早期に発見することができ、適切な対策を講じることができます。これにより、電気設備の長寿命化や安定した運用が可能となり、事業活動の継続性や安全性の向上に大きく貢献します。
点検の対象となる電気工作物
点検を義務付けられている電気工作物について解説していきます。
一般用電気工作物
一般用電気工作物とは、事務所や住宅、小規模店舗などで使用される、電圧600ボルト以下で受電する電気設備を指します。一般家庭用の太陽光発電設備や屋内配線もこれに含まれます。電圧が低いため保安に関する規制は比較的少ないものの、基本的な安全基準は遵守しなければなりません。点検では、設備の劣化や損傷、漏電の有無などをチェックし、必要に応じて修理や交換を行います。
事業用電気工作物
事業用電気工作物とは、一般用電気工作物には当てはまらない工作物で、電力会社の発電所、ダム、変電所、送電線路、配電線路など、高電圧を使用する設備が含まれます。これらは工場や電力会社などが広範囲に電気を供給する際に使用する設備のため、電力の安定供給と安全確保のためには適切な管理と点検が求められます。電気保安点検において、特に重要な対象となっています。
自家用電気工作物
事業用電気工作物の中でも、600ボルト以上で受電する工場やビルの変電設備、中小ビルやマンションのキュービクルや屋内外配線が対象となります。自家用電気工作物の保安点検は、通常は電気主任技術者が行います。ただし、外部委託承認制度を利用することで、専門業者への委託も可能です。
電気設備の安全点検「電気保安点検」が必要とされる理由

電気設備の安全性を維持するためには、定期的な保安点検が欠かせません。設備の経年劣化や絶縁体の劣化は、漏電や感電のリスクを高め、最悪の場合、火災に至る危険性すらあります。事故や停電を防止して、万が一重大な事故が発生してしまった場合でも法的責任を回避するためには、定期点検は避けて通れません。また、法令で定められた技術基準や設置基準を遵守することは、電気設備の安全かつ効率的な使用を保証する上で重要な役割を担っています。
特に、産業用自家消費型太陽光発電の施工を安全に進めるためのポイントについては、「産業用自家消費型太陽光発電の施工プロセス 完全ガイド」で詳しく解説しております。
電気保安点検の4つの種類

電気保安点検は、事故予防のために非常に重要な役割を果たしています。この点検には4種類あり、使用する電気設備の種類によって、点検内容やタイミングが異なります。定期的な確認と適切な実施が求められており、それを忘れずに行うことが事故防止の鍵となります。では、4つの電気保安点検について、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
月次点検
原則として毎月1回行われるこの点検では、使用中の電気工作物、機材、設備を運転中の状態で点検し、必要に応じて測定も実施します。電気保安の作業員が配線の状態や保安装置を目視でチェックし、電圧や電力の測定を行って過負荷の有無を確認します。さらに、設備の劣化状況や亀裂の有無も調べることで、安全性を維持しているのです。
点検中に異常が確認された場合は、直ちに使用責任者に報告して、適切な対策を講じることが求められます。点検結果は点検報告書に記録され、この報告書は3年間保管する義務があります。点検の頻度や内容は、使用されている施設や機材の種類、使用環境によって異なり、必要に応じて隔月や3ヶ月ごとの点検に調整することも可能です。電気保安点検の詳細情報や具体的な対応については、電気保安を専門とする電気管理技術者(電気主任技術者)に相談することが最も確実な方法でしょう。電気管理技術者は、電気設備の安全性を維持するための知識と経験を持っており、適切なアドバイスを提供してくれます。
年次点検
年に1回行われる年次点検は電気保安点検の中でも最も重要な点検です。停電年次点検とも呼ばれています。この点検では、電気工作物を停電状態にして絶縁抵抗の測定を行うほか、機器内部の点検、部分放電の確認、機器温度の測定などを実施します。点検時には通常、クリーニングも同時に行われ、機器の性能維持と事故防止にも寄与しています。
ただし点検は停電を伴う作業であるため、ビジネスへの影響を最小限に抑えるための配慮が必要であり、事前に点検業者との詳細な打ち合わせが求められます。点検の結果、法的基準に達していない場合は、速やかな状況改善措置が必要となります。信頼できる専門業者による適切な保守が強く推奨されますし、重大な事故が発生した際は、関連部署への迅速な報告義務が生じます。
通常は年に1回の点検が必要とされますが、一定の条件を満たす場合には、3年に1回まで頻度を延長することが可能です。その条件には、設備が特定の安全要件を満たしていることや、無停電点検を適切に実施していることなどが含まれます。しかし、点検報告書の作成と保管は依然として義務付けられています。年次点検は電気保安の要であり、適切な実施と管理が強く求められる重要な業務と言えます。
臨時点検
定期点検とは別に、臨時点検という特別な点検も存在します。この臨時点検は、電気設備の異常や危険が予想される場合に実施されるもので、迅速な対応が求められる重要な点検です。
特に梅雨時期や雷雨が多発する時期、降雪や降灰がある地域では、電気設備にトラブルが起こりやすくなるため、事前の臨時点検が推奨されています。また定期点検で何らかの異常が発見された場合や、悪天候により事故の可能性が高まった時にも、臨時点検を行って原因を突き止め、適切な修理や事故防止策を講じることが大切です。潜在的なリスクを回避するためにも、専門業者との連携を密に取りながら、必要に応じて定期的な実施の検討をしてください。
事故対応
事故対応は、迅速な対処が求められる点検業務の1つです。停電や漏電などの電気事故が発生した際に行われる点検です。迅速な対応が求められるため、信頼のおける専門業者との連携が非常に重要となります。現場の状況確認後、必要に応じて送電停止などの応急処置を施し、事故原因を調査します。問題解決後は、再発防止のための適切な対策を講じることが求められます。また、作業員や担当者が迅速に対応できる体制の整備も重要です。
電気保安点検(法定点検)後の報告書とは?

電気保安点検(法定点検)の報告書には、電気設備の不具合や異常が「指摘事項」と「指導事項」の2つに区分されて記載されます。「指摘事項」は、電気事業法の「電気設備の技術基準」を満たしていない法律違反の状態を指し、一方、「指導事項」は法令違反ではありませんが、設備の劣化等があり、修理や交換が推奨されるものです。
事業者の責任者は、この報告書を確認して、必要に応じて改修計画を策定する必要があります。特に、指摘事項は火災や感電の事故につながる可能性もあるため、早急な対応が求められます。電気設備の安全な使用を保証するためには、これらの改修が重要となります。
停電年次点検の頻度は減らすことができる

停電を伴う年次点検は、ビジネスへの影響が大きいため、多くの事業者が早朝や休日に実施することで、業務停止を回避しています。しかし、特定の条件を満たせば、この点検を3年に1回に減らすことが可能です。その条件とは、点検対象の設備が適切に管理されており、故障や不具合の発生リスクが低いと判断される場合です。この条件を満たすことで、残りの2年は無停電点検で実施することが許可されます。無停電点検では、設備を停止させずに点検を行うため、業務への影響を最小限に抑えることができます。その条件について詳しく解説します。
4つの条件を満たす場合
停電年次点検の頻度を減らすには、事業場の設備条件が4つの条件を満たすことが求められます。この条件をクリアすることで、点検頻度を3年に1回に縮減できるようになります。
まず、高圧変圧器が柱の上に設置されておらず、高圧負荷開閉器に可燃性絶縁油が使用されていないことが必要不可欠です。次に、地絡遮断器が設置されている必要があります。最後に、主遮断器用の開閉状態表示用変成器や主遮断器操作用の変成器以外の変成器が設置されていないことが条件となります。これら4つの設備条件を満たすことで、事業場は安全基準が高いと判断されます。その結果として、点検頻度の緩和が認められます。
特定の条件に一致する場合
通常は前述の「4つの条件」を満たす必要がありますが、次のいずれかの条件に一致する場合には、2つの条件のみで、3年に1回の実施に減らすことができます。
その条件とは、可燃性絶縁油を高圧負荷開閉器に使用していないことを前提に、地絡遮断器を設置している事業場であることか、地絡保護継電器付きの高圧交流負荷開閉器を設置している事業場であることです。
無停電点検とは?
停電年次点検の回数を減らすことができた場合、その間に実施する無停電点検について解説します。無停電点検では、電源を切ることなく年次点検を実施します。通常業務の最中でも実施することができ、電源を切らずに機器の状態を確認できるため、作業の中断が不要という大きなメリットがあります。
点検には特殊な機器が用いられます。例えば、コロナ放電チェッカーで絶縁体の劣化を確認し、赤外線放射温度計を使って機器の温度異常を検知します。無停電点検でも点検の精度は十分であり、異常箇所を早期に発見し、大きな問題に発展する前に対処できた事例も報告されています。業務の継続性を維持しつつ、設備の安全性と信頼性を確保する上で効果的な手法と言えるでしょう。
法定停電とは?

電気事業法に基づき、年に一度必須で実施される点検「年次点検」では、停電することが求められます。それが法定停電と呼ばれます。この停電は電気事業法の第42条と保安規程により規定されており、一定以上の電力を使用する事業用電気工作物、主にキュービクルと呼ばれる高圧受電設備を持つオフィスビルや工場などが対象となります。主に、高圧で電気を受け入れ、キュービクルと呼ばれる設備で使用電圧に変換している施設が影響を受けます。
キュービクルでは、変圧器やブレーカーを含む複数の電気設備の点検を行い、漏電やその他の異常がないかを確認します。もし不具合が発見された場合、予期せぬ全館停電や感電事故、火災、波及事故などの重大なリスクが発生する可能性があります。これらの事故を防ぐために、定期的に全館停電を実施し、電気設備に対しての徹底的な点検が行われるのです。この点検は、施設の安全を維持し、大きな事故や賠償問題への発展を防ぐ上で極めて重要な役割を果たしています。
法定停電では事前対策が重要
法定停電が実施される際には、電力を必要とする機器類の停止によるデータ損失やシステム障害、セキュリティ設備の機能停止による安全面でのリスク増大など、様々な問題が生じる可能性があります。さらに、電力復旧時には埃による通電火災や回線のショートによる機器の故障といった二次災害のリスクも伴います。
そのため、法定停電を行う際には、事前準備が非常に重要です。適切な故障防止策を講じることで、業務の遅れや売上の損失を防ぐことができます。停電に備えた具体的な準備について詳しく解説していきます。
対策内容
法定停電では、電力に依存する機器やシステムへの影響が大きいため、事前の対策が重要となります。まず、予備の停電用バッテリーの使用を検討しましょう。ただし、バッテリーの稼働時間を事前に確認しておく必要があります。次に、シャットダウンが必要な機器やソフトウェアをリストアップし、操作手順をマニュアル化しておくと良いでしょう。
データは万が一の場合に備えて、バックアップを取っておきましょう。加えて、バックアップのリカバリプロセスまで試しておくことが望ましいです。さらに、停電前にはファンの清掃やACアダプターの切り離しまで行っておき、機器の故障を未然に防ぎましょう。
また、緊急時の連絡先を明確にしておくことで、トラブル発生時の迅速な解決が可能になります。復旧後、すべての機器が正常に機能するとは限らない点にも注意が必要です。法定停電に備えて、これらの対策を事前に実施しておくことが重要です。万全の準備を整えることで、停電による影響を最小限に抑えることができるでしょう。
停電解消後にするべきこと
法定停電後の機器やシステムの再起動は、慎重に行う必要があります。停電による損傷やデータ損失の可能性を考慮し、マニュアルに沿った正しい手順での立ち上げと、試運転による問題の有無の確認が重要となります。再起動前の点検と適切な手順の遵守が、機器やソフトウェアの安全な運用につながるでしょう。
電気設備の安全点検「電気保安点検」の課題

電気設備点検を行う企業には、技術面での困難さや安全基準への対応など、様々な課題が立ちはだかります。本記事では、そうした課題の中でも特に重要な2つの課題を取り上げ、詳しく解説していきます。
再生可能エネルギー設備とリスクの増加
FIT制度の導入により、太陽電池や風力発電設備の数が急速に増加しています。しかし、再生可能エネルギー設備の急増は、変電所や送配電線路などの高圧電力設備での事故リスクも高めており、安全への懸念が強まっています。そのため、点検と安全対策の徹底が急務となっています。再生可能エネルギー設備における安全確保は、今後のエネルギー政策を左右する重要な課題とも言えます。
安全点検に関わる人手不足
電気設備の点検分野では人手不足が深刻化しており、特に専門資格を持つ人材の減少と高齢化が顕著です。この傾向が続けば、将来的にさらなる人材不足を招く可能性が高いとされています。保守点検業務では作業員個々の経験や技能が大きく影響するため、新規人材の育成が難しいという課題も存在し、技術力の低下が懸念されています。従来の点検作業は、巡回検査や従業員の手作業が主体であり、作業負担が大きく人的ミスの原因ともなっています。
災害などの緊急事態発生時には、設備の遠隔監視が困難となり、迅速な対応ができなくなるリスクも伴います。電気設備の安全点検における人手不足問題は、多くの課題が複合的に絡み合っているため、その解決は容易ではありません。今後も人手不足問題の深刻化が予想され、効果的な対策の実施が急務となっています。
電気保安点検の今後

電気保安点検は現在、大きな変革の時期を迎えています。従来の、担当者が現場に赴き目視で確認するアナログな方法から、遠隔での設備監視や点検頻度の調整といった新しい方式への移行が求められています。人材不足や設備の増加を背景に、従来の方式の継続性に疑問が生じているのです。
技術革新により、月次点検を含む設備の監視を遠隔で行うことが可能となり、点検頻度の自由度も高まっています。また、高い保安技術を持つ事業者に対しては、自主的に行える保安作業の範囲を広げることも検討されています。
加えて、主任技術者の配置義務の緩和など、規制の見直しも進められています。例えばある地域では、既に一人の統括電気主任技術者のもと、最短で2時間以内に担当技術者が電気工作物の設置場所に到達可能な体制が許容されています。ただし、その際にはスマート保安技術を含む複数の措置による電気設備の安全性確保が必要とされます。
ITやIoTを利用した点検の遠隔監視や自動化も進展しており、現場の省人化や管理業務の負荷軽減が図られています。さらに、点検データの蓄積による業務の質の向上やトラブルの早期発見も可能になっています。電気保安点検は、より効率的かつ効果的な方法へと進化しつつあります。安全性を確保しながら、いかに合理的な点検体制を構築できるかが、今後の重要な課題と言えるでしょう。
太陽光発電設備の安全点検

電気設備の中でも、太陽光発電設備において安全点検は非常に重要です。そのため、個別に取り上げさせていただきます。理由は大きく分けて3つあります。
まず1つ目は、2017年の改正FIT法により、太陽光発電設備の定期点検が義務化されたことです。法令違反時には指導や認定取り消しの可能性があり、発電事業の継続ができなくなる恐れがあります。2つ目は、定期的な安全点検により発電効率の低下を防ぎ、設備の長寿命化が図れることです。太陽光パネルの汚れや破損、接続不良などを早期に発見し、適切なメンテナンスを行うことで、安定した発電量を維持することができます。
3つ目は、事故防止の観点からも安全点検が重要だということです。安全点検を怠り、故障や不具合を放置したことによる電気火災や、強風による太陽光パネルの飛散といった事故が報告されています。太陽光発電設備の事故は、該当設備だけではなく周囲に損害を及ぼすこともあり、事故が発生してしまった際の被害は甚大です。
このように、太陽光発電設備の安全点検は、法令遵守、発電効率の維持、事故防止の観点から非常に重要です。定期的な点検を実施し、適切なメンテナンスを行うことで、安全で安定した発電事業を継続することができるのです。
まとめ
電気保安点検は、電気設備の安全性を確保するための法定義務であり、月次点検、年次点検、臨時点検、事故対応の4種類があります。特に年次点検では停電を伴うため、事業への影響を考慮した入念な準備が必要です。特定の条件を満たすことで、3年に1回に減らすことができ、また、無停電点検を活用することで、業務への影響を軽減することが可能です。停電を伴う法定停電を行う場合には、事前準備と点検後の改修がとても重要です。点検への正しい理解と、適切な実施を心がけてください。
一方、再生可能エネルギー設備の増加によるリスクの増加や人手不足といった課題も顕著です。これらの問題解決には、遠隔監視やスマート保安技術の導入が進められており、効率的で安全な管理体制の構築が期待されています。電気保安点検は、電気設備の寿命や安全性を高めるために欠かせないものです。定期的かつ適切な実施を行い、安全で効率的な電気設備の運用を実現しましょう。
特に太陽光発電設備については、事故防止の観点からも点検が欠かせません。怠った場合には電気火災やパネルの飛散事故などが発生するリスクがあり、設備だけでなく周囲にも損害を及ぼす可能性があります。定期的に点検を実施して、適切なメンテナンスを行うことで、安全で安定した発電事業の継続が可能となります。
このように、EPC事業者には、電気設備の安全点検に安心できる運用体制が求められています。
しかし、それだけでは十分とは言えません。
特に産業用自家消費型太陽光発電においては、設計・施工の品質や電力会社との申請手続き、トラブル発生時の対応など、スムーズな導入と安全な運用のために押さえるべきポイントが数多くあります。
施工をスムーズに進めるための具体的なノウハウを、以下の資料で詳しく解説しております。