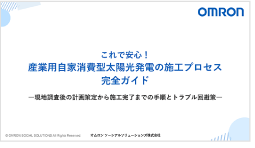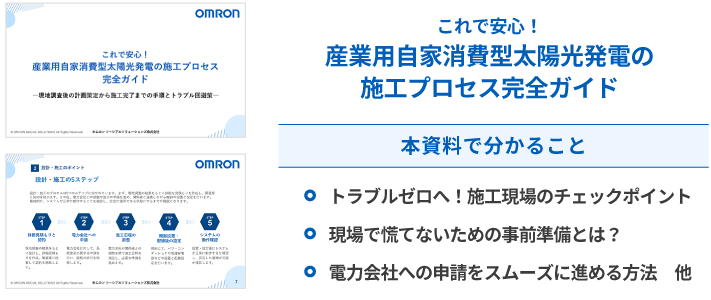お役立ち情報
電気設備工事とは?電気工事との違いから、種類や必要な資格まで詳しく解説

電気設備工事とは、電気を使用する設備を整える工事のことです。単に電気を通すだけでなく、安全に利用するための設計や施工まで含まれます。照明設備工事や動力設備工事、受変電設備工事など、さまざまな種類があります。それぞれに独自の仕事内容や要求される専門知識があるため、種類に応じて必要な資格やプロセスを理解することが重要です。
本記事では、電気設備工事の種類から、資格が求められる理由まで詳しく解説します。電気設備工事について理解を深めることで、適切な工事業者の選定や、安全で効率的な電気設備の整備に役立つでしょう。
目次
電気設備工事とは?

電気設備工事とは、電力会社から供給される電気を建物内で安定して供給するため、建物に必要な電気を引き込む工事のことです。電気工事士の資格を持つ専門家が、建物の分電盤からコンセント、照明まで電気が使用できる状態にすることを指します。
この工事は、住宅、商業施設、工場など様々な建物で行われます。電力量計の設置や電気供給の申請から、最終的なコンセントの配置まで幅広い作業が含まれます。また、高圧電気を低電圧に変換して配分する業務や、通信設備の設置及び増設作業にも対応しています。通常、電気設備工事は建設工事と並行して進められ、壁に穴を開けたり特定の機器を設置する作業が含まれます。電気設備の設置後も、定期的な点検やメンテナンス、必要に応じた修理を行うことが電気設備工事に含まれます。日常生活に不可欠な工事です。
電力の引き込み方の違い
電気設備工事は主に「架空線方式」と「地中化方式」の2種類に分けられます。「架空線方式」は、電力会社の電柱からケーブルを引き込み、敷地内に配線を行う方式です。この方式のメリットは、工事費用が比較的低いことですが、災害時のリスクが高まる点と景観が悪化することがデメリットとして挙げられます。
一方、「地中化方式」では、電流路を地中に埋設し、中継ボックスを経由して受変電設備に繋げます。この方式は露出部分がないため、災害に強いというメリットがあり、特に都心部での採用が多くなっています。しかし、工事費用が高くなるというデメリットもあります。これらの方式は、それぞれのメリットとデメリットを考慮し、設置環境、予算、求められる安全性などによって比較検討された上で、最適な方式が決定されます。
電気工事との違い
電気設備工事とよく混合される電気工事との違いについて理解しておきましょう。電気設備工事は、コンセント、スイッチ、照明などの電気を使用するための設備を設置する工事のことです。これは電気工事の一部として位置づけられます。一方、電気工事は電気設備の設置工事だけでなく、各種配線工事や設計など、電気に関する工事全般を指します。つまり、電気設備工事は電気工事の一部であり、電気工事はより広範な業務をカバーしています。
したがって、電気設備工事と電気工事は密接に関連していますが、その業務範囲には違いがあることを理解しておくことが重要です。
電気設備工事の重要性

現代社会において、電気設備工事の重要性は日々高まっています。電気は私たちの生活に欠かせない存在であり、照明や通信機器、さらには医療機器に至るまで、多くの機能の基盤となっているからです。もし電気の供給が途絶えれば、日常生活や業務が一時的に停止され、混乱が起きる可能性があります。
また、電気設備工事が不適切に行われた場合、火災や感電事故のリスクが増大します。これらは人的、物的な被害に直結するため、適切な工事の実施が求められます。さらに、効率的な電気設備工事は省エネルギー対策や環境保護にも寄与します。その実現のためには、最新の技術を活用した工事が不可欠です。このように、電気設備工事は現代社会を支える重要な役割を担っているのです。
電気設備工事の種類

電気設備工事には、照明設備の工事や、動力設備、受変電設備の工事など様々な種類があります。それぞれ必要とする技術や専門知識が異なり、建物の用途や規模によって適用される種類も変わってきます。代表的な種類について詳しく解説します。
受変電設備の工事
受変電設備は、発電所から送られてきた高圧の電力を、建物内で利用可能な低圧に変換する重要な装置です。オフィスビルや工場といった電力消費量が多い施設では不可欠な設備ですが、店舗、ホテル、学校など大規模な建物でも必要とされます。一方、家庭用としての小規模な受変電設備も存在します。
受変電設備の工事は、建物の用途や電力需要に応じて、その種類と規模が異なります。大規模な施設では、高圧受電設備や変圧器、配電盤などを設置し、安定した電力供給を確保します。一方、小規模な建物では、より簡易な設備で対応することができます。いずれの場合も、専門家による適切な設計と施工が求められます。
幹線・分岐回路工事
電気設備工事において、幹線・分岐回路工事は建物全体への電力供給を担う重要な工事です。幹線は、電気が建物に引き込まれる引込口から各分電盤、または配電盤から分電盤までの配線を指します。建物全体に電力を分配する役割を果たしています。一方、分岐回路は分電盤から各電気機器や照明などへ直接接続される配線部分で、特定の機器へ電力を供給します。
これらの幹線と分岐回路を適切に設計し、施工することで、建物内のすべての電気機器に安定した電力供給が可能となります。電気設備工事の中でも、幹線・分岐回路工事は建物の電気システムの根幹をなす重要な工程といえるでしょう。
コンセント設備の工事
電気設備工事には、コンセントの設置と配線が含まれます。この工事を進めるにあたっては、発注者と密接に協議しながら、使用する電気器具に応じたコンセントの数と配置を決定していく必要があります。計画段階では、各場所に必要なコンセントの数を正確に把握することが必要とされます。適切なコンセントの設置と配線を行うことで、安全かつ効率的な電気設備の利用が可能となるのです。
動力設備の工事
動力設備は、電気を動力源として稼働する機械設備のことを指します。代表的なものとしては、エアコン、冷蔵庫、エレベーター、スプリンクラー、給水ポンプなどが挙げられます。これらの設備は、一般家庭で使用される100Vの電力では不十分であり、200Vの高電圧が必要となります。そのため、専用のコンセントやブレーカーを通して電力を供給する必要があります。
照明設備の工事
建物に照明を設置する電気設備工事には、新しい照明の設置だけでなく、古い照明器具をLEDに交換する作業も含まれています。施工前には、施設の形状や発注者の要望を確認し、経済性と効率性を考慮した計画を立てることが重要です。LEDは白熱電球や蛍光灯に比べ、長寿命で消費電力が少ないというメリットがあります。建物の用途や規模に合わせて最適な照明器具を選定して、適切な位置に配置しましょう。
情報通信設備の工事
情報通信設備の工事は、建物内でインターネットやテレビを利用するために必要不可欠です。LANケーブルの敷設、ルーターや電話設備の設置、テレビ配線などが具体的な工事内容として挙げられます。また、放送設備、テレビ共聴設備、時計設備、車路管制設備などの特殊な設備の工事も含まれます。近年、情報通信技術の発展に伴い、情報通信設備工事の需要は高まっています。
防災設備の工事
電気設備工事の中でも、防災設備の工事は非常に重要な役割を担っています。火災検知器や警報機、誘導灯、非常放送設備などの設置工事は、火災発生時に人命と建物を守るために欠かせません。これらの設備は、火災の発生を早期に検知し、避難誘導や消火活動に役立ちます。また、防災設備は定期的なメンテナンスが必要不可欠です。故障や不具合を放置すると、いざという時に機能しない可能性があるため、常に最適な状態を保つ必要があります。
近年、防犯関連の設備工事の需要も高まっています。監視カメラの設置などがその一例ですが、設置位置に電源がない場合、新たにコンセントを設置する必要があります。火災報知器やマンションの誘導灯も電気を使用するため、定期的な点検が欠かせません。安全で確実な運用を確保するためには、適切な管理体制の構築が求められます。
オール電化住宅向けの工事
オール電化住宅は、ガスを一切使用せず、すべてのエネルギーを電気で賄うシステムです。給湯、調理、床暖房など、住宅内のあらゆる設備に電気が使われます。具体的には、エコキュートやIHクッキングヒーターなどの機器が導入されることが多く、これらは火を使わないため安全性が高く、火災リスクや二酸化炭素の放出も抑えられます。
ただし、オール電化住宅では電気の安定供給が欠かせません。適切な電気配線とアンペア数の設定が重要であり、電気設備の不具合でブレーカーが頻繁に落ちるようであれば、専門家による診断や電気設備工事が必要になるかもしれません。オール電化住宅の電気工事は通常、半日から3日程度で完了します。
さらに、太陽光発電システムとオール電化を組み合わせることで、災害時の電力供給の安定性が向上します。例えば、太陽光発電で得られた電力を蓄電池に貯めておくことで、停電時にも一定期間、電気を使用することができるようになります。オール電化住宅への電気設備工事は、安全性や利便性、そして災害対策の面からも重要な意味を持っているのです。
太陽光発電設備の工事
環境意識の高まりやBCP対策などから、近年多くの住宅や企業で太陽光発電設備の導入が進んでいます。2025年からは東京都で新築住宅への太陽光パネル設置が義務化される予定もあり、再生可能エネルギーのさらなる普及が目指されています。太陽光発電設備の工事は電気工事士によって行われ、パネルの設置から配線、パワーコンディショナーの接続まで一貫して担当されます。また、設置後の定期的なメンテナンスや点検も重要な工事の一部です。
施工の種類によって注意すべきポイントは異なります。特に産業用太陽光発電の施工では、計画から試運転までの流れを正しく理解しておくことが重要です。詳しくは「産業用自家消費型太陽光発電の施工プロセス 完全ガイド」で詳しく解説しております。
電気設備工事に資格が求められる理由

電気設備の工事には専門的な知識と技術が必須であり、無資格者が行うことは非常に危険です。不適切な扱いにより、低圧(100〜200V)の家庭用電気であっても、感電死亡事故が起こる可能性があります。また、漏電により火災が発生するリスクもあります。
したがって、電気設備の工事は資格を持った専門家に依頼することが重要です。資格者による適切な工事が、安全で安心な電気の使用につながります。無資格者による工事は自身だけでなく、周囲の人々の生命や財産を脅かす危険性があることを認識しておきましょう。
電気設備工事に必要な資格

電気設備工事を行う上では、法的に必須の資格と、必須ではないが持っているとより安全であったり、工事の範囲が広がる資格があります。必須の資格としては、「第一種電気工事士」や「第三種電気主任技術者」などが挙げられます。一方、「職長・安全衛生責任者」などは必須ではありませんが、持っていることで安全性の向上や作業効率のアップが期待できます。代表的な資格について詳しく解説していきます。
必須の資格
電気設備工事を行うには、法律で定められた特定の技術系国家資格の取得が必須です。詳しく解説します。
2級電気工事施工管理技士
電気工事施工管理技士は、電気設備工事や変電・発電設備工事の施工管理技能を認定する国家資格です。この資格には1級と2級が存在し、それぞれの等級によって担当できる工事の規模や役割が異なります。1級資格保持者は、特定建設業の専任技術者や管理技術者として大規模な建設工事現場での活動が可能です。
一方、2級資格保持者は一般建設業で、専任技術者や主任技術者として主に中小規模の現場で活躍します。電気工事施工管理技士の主な業務は、施工計画の立案、工程管理、安全管理、品質管理などです。また、電気設備の定期点検や空調設備の管理も担当します。この資格を持つ者は、電気設備工事における適切な施工と管理を行うことで、安全で質の高い工事の実現に貢献しています。
1級電気工事施工管理技士
1級電気工事施工管理技士は、電気工事における現場の最高責任者として、工事の品質管理や安全管理を担う重要な資格です。2級電気工事施工管理技士の上位資格であり、特定の建設業における営業所ごとに必要とされる専任技術者や現場の監理技術者としての役割を果たすことができます。この資格を取得するには、第一次検定と第二次検定の両方に合格する必要があります。1級電気工事施工管理技士の資格を持つことで、専任技術者や主任技術者に加え、監理技術者としての業務を担うことが可能となり、電気工事における技術力と管理能力の高さが証明されます。
第三種電気主任技術者
第三種電気主任技術者は、電気主任技術者の資格の1つであり、電験三種とも呼ばれます。電気主任技術者は、電気事業法で定められた電気の専門家であり、電気設備の運用管理を独占業務として行います。電気主任技術者には一種から三種までの区分があり、扱える電圧の範囲が異なります。
第一種は全ての電気工作物、第二種は17万ボルト未満の電気工作物、第三種は特定発電所を除く5万ボルト未満の電気工作物を扱うことができます。第三種電気主任技術者の資格を取得すれば、中小規模の工場、商業施設、病院、太陽光発電所などで保安監督業務を行うことが可能です。電気設備の安全性を確保し、法令に基づいた適切な管理・運用を行うことが第三種電気主任技術者の重要な役割となります。
第二種電気工事士
第二種電気工事士は、600V以下の低圧電気工事を行うために必要不可欠な国家資格です。この資格は経済産業省によって定められており、学歴や職歴、就労経験に関係なく、誰でも受験することができます。近年、巣ごもり需要によるエアコンの設置工事の増加やマンションの建設ラッシュにより、第二種電気工事士の需要が高まっています。電気工事の安全性を確保し、トラブルを未然に防ぐためにも、この資格の取得が強く推奨されています。
第一種電気工事士
第一種電気工事士は、自家用、一般用、小規模事業用の各種電気工作物の工事を担当できる、電気設備工事において必須の国家資格です。自家用電気工作物では、高圧で受電した電気をキュービクルで低圧に変換し、屋内配線や配電盤を経由して情報機器や動力設備に電気を供給します。一般用電気工作物は低圧で受電する一般家庭や商店の電気設備を指し、小規模事業用電気工作物には出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備などが含まれます。
第一種電気工事士は下位資格の第二種電気工事士より上位に位置し、ほとんど全ての電気設備工事に携わることができるため、多岐にわたる業務を担当することが可能です。この資格を取得することで、電気設備工事の現場で幅広く活躍できます。
認定電気工事従事者
認定電気工事従事者は、第二種電気工事士の資格のみでは対応できないマンションやビルなどの簡易電気工事を行える国家資格です。第二種電気工事士を取得した人が、対応可能な工事の幅を広げるために取得することが多くなっています。試験はなく、講習の受講のみで資格を取得できるのが特徴です。この資格を取得することで、より多様な電気工事に従事することが可能になります。
特殊電気工事資格者
特殊電気工事資格者は、自家用電気工作物における特定の工事を行うことができる国家資格です。この資格は主に、「ネオン工事」と「非常用予備発電装置工事」に限定されていて、これらの工事を行う際には必須とされています。これらの工事を行うためには、第一種電気工事士や第二種電気工事士、認定電気工事従事者の資格だけでは不十分です。特殊な工事に対応できる知識や技術が十分ではないためです。そこで、必要な講習を受けて特殊電気工事資格を取得する必要があります。
持っていると安全、便利な資格
続いて、必須ではありませんがより安心安全な工事を行うため、工事の幅を広げるために持っておく便利な資格を紹介します。
職長・安全衛生責任者
職長・安全衛生責任者は、作業員への教育指導や工具の点検、安全の確保を担います。結果として、電気設備工事現場における事故の防止や作業の効率化が図られます。資格を取得するには、所定の教育を受ける必要があります。教育を通じて、現場の指揮や監督のための知識やノウハウを身に付けられるのです。
電気取扱者
電気設備工事に携わる上で、低圧電気取扱者と高圧・特別高圧電気取扱者の資格は非常に重要です。これらの資格は、各電圧レベルに対応した電路や電路支持物の敷設、点検、修理、操作を安全に実施するために必要とされています。低圧電気取扱者は600V以下、高圧・特別高圧電気取扱者は600Vを超える電気設備を扱うことができます。資格取得には、専門の講習を受講し、筆記試験と実技試験に合格する必要があります。
高所作業車運転技能
この資格は、作業床の高さが10メートル以上の車両を運転する際に必要とされます。所定の講習を受講し、修了試験に合格することで資格を取得できます。さらに、道路上で高所作業車を運転する場合は、自動車免許の所持が必須条件となっています。この資格を持っていることで、より安全に電気設備工事を行うことができるでしょう。
車両系建設機械運転者
この資格は労働安全衛生法に基づいて設定されており、特定の建設機械を運転するには必須となっています。対象となる機械には、3トン以上のパワーショベルなどが含まれ、主に大規模な土木工事で使用されます。電気設備工事でも、地中に電線管を埋める作業などではパワーショベルの使用が不可欠です。そのため、運転者はこれらの機械を安全に操るためのスキルを身につける必要があります。
電気設備工事後はメンテナンスが重要

電気設備の工事後は、定期的なメンテナンスが非常に重要です。電気設備の不調は、火災や感電のリスクを高めます。そのため、定期的なメンテナンスを行い、問題を事前に修繕することで安全を確保することが大切です。また、故障を防ぐことで、修理費用や事故時の業務の中断を回避できますので、結果的にコスト削減にも貢献します。
特に、太陽光発電設備などの電気設備においては、メンテナンスが設備の寿命延長と安定稼働に不可欠です。定期的なメンテナンスにより、システムの故障や発電量の低下を防ぎ、発電効率を維持することができます。これにより、運用コストの削減にもつながります。
電気設備工事を依頼する際は、工事後のアフターサービスやメンテナンス対応も含めて、施工業者を比較検討することが重要です。信頼できる施工業者を選ぶことで、長期的な安全性と経済性を確保してください。
まとめ
電気設備工事は、建物に電気を引き込み、照明やコンセントを設置する工事であり、現代の日常生活には欠かせません。受変電設備、幹線・分岐回路、動力設備、照明設備、コンセント設備など、様々な種類の工事が含まれます。
これらの工事を適切に行うには、専門的な知識と技術の両方が必要不可欠です。そのため、第一種・第二種電気工事士などの国家資格を持つ専門家が施工することが求められています。資格を保有する専門家が工事を行うことで、安全性を保ち、事故を未然に防ぐことができるのです。
このように、電気設備の工事には様々な専門知識や技術が必要とされる中、EPC事業者には、細かな計画と正確な工事が求められます。
特に産業用自家消費型太陽光発電の導入では、現地調査・設計・施工・試運転の各ステップで注意すべきポイントを押さえておくことが不可欠です。
施工の流れやトラブル回避策、電力会社との申請手続き、設置時の重要ポイントなど、施工をスムーズに進めるための具体的なノウハウを、以下の資料で詳しく解説しております。