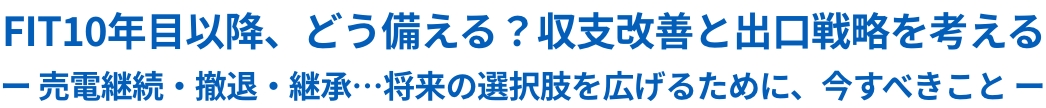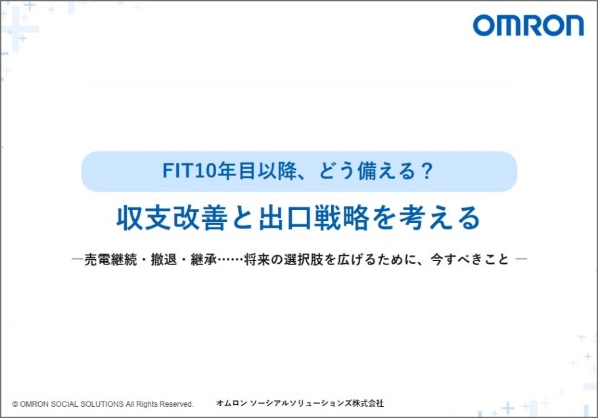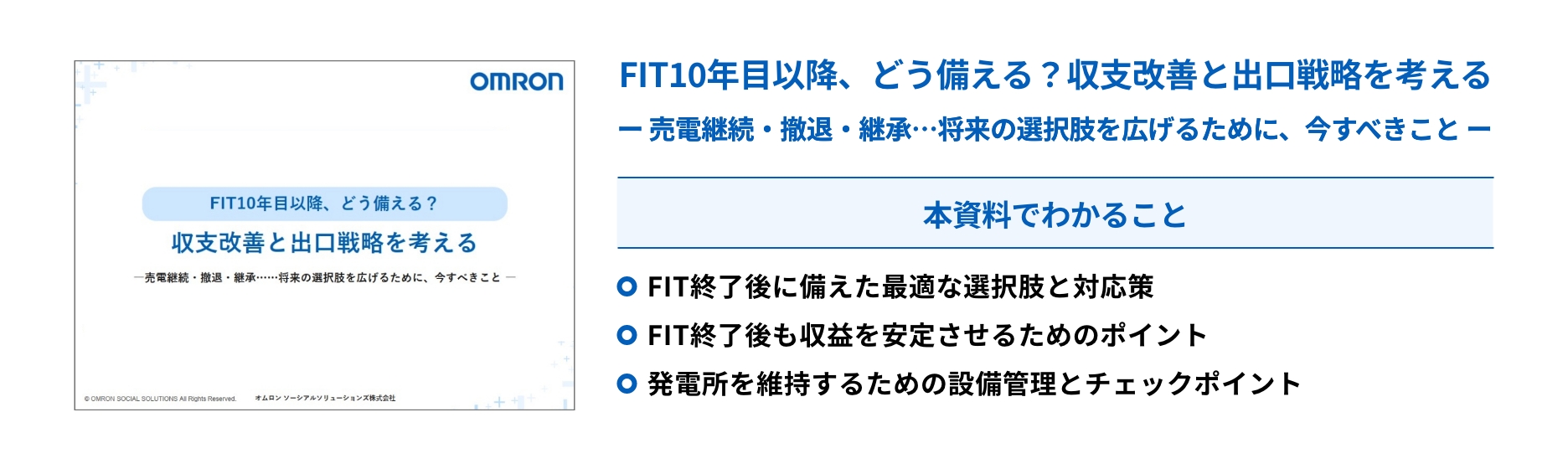出力制御への対策と見通し【2025年度最新】売電収入を減らさないための運用ノウハウ

近年、太陽光発電分野では出力制御の実施が全国的に広がりを見せており、投資の観点からも軽視できないリスクとして認識されはじめています。2023年度には特に九州エリアにおいて大規模な出力制御が行われ、国内全体での出力制御量は18億kWhに達しました。この結果として、多くの発電所が一時的に売電を停止せざるを得ず、収益減少という課題に直面しています。本記事では、出力制御の仕組みから、発電事業者が取るべき対策まで詳しく解説します。
目次
出力制御とは?

出力制御とは、需要を上回る電力が発電された際に、発電量を意図的に抑える仕組みのことです。電力の需給バランスを維持するための措置であり、「出力抑制」とも呼ばれています。電力会社が発電事業者に対して、出力の一部停止や抑制を求めるかたちで行われます。
なぜこのような調整が必要なのでしょうか?電力の需給は常に一致していなければならず、このバランスが崩れると、系統周波数に影響を及ぼします。たとえば、需給が釣り合わずに周波数が低下すると需要超過、高まると供給過剰とされ、結果として設備に不具合が生じたり、大規模停電のリスクが高まったりする恐れがあります。
また、家庭や工場、蓄電池といった需要設備には、消費できる電力量に限界があります。このため、需要が落ち込む時間帯には、ベースロード電源を除外したうえで、残る発電設備によって全体の出力を調整するのが一般的です。
特に太陽光発電は、気象条件によって出力が大きく変動するため、出力制御の対象となりやすい傾向があります。2023年度には、全国で実施された出力制御によって、合計18億kWhもの電力量が抑えられました。今後、電力の安定供給を実現していくうえで、出力制御の重要性はさらに高まることが予想されます。
需給バランスを維持することの重要性
電力の需給バランスを維持することは、大規模停電を防ぐうえで不可欠です。もし供給が過多になったり、需要が不足したりすると、電圧や周波数に乱れが生じ、送配電設備に接続された電子機器が異常を検知し自動停止してしまいます。これが連鎖的に広がると、大規模停電につながる恐れがあります。このようなリスクを予防する手段として、発電量を調整する出力制御が重要とされています。
出力制御要請への対応義務
出力制御が実施されると、FIT制度(固定価格買取制度)によって電力を売電している発電事業者の収入は減少します。そのため、こうした要請にどこまで応じるべきか、疑問を持つ事業者も少なくありません。しかし、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(いわゆる「再エネ特措法」)」では、出力制御の要請に応じることが義務として定められています。
さらに、FIT制度の認定を受けた時点で、発電事業者は出力制御の要請に従うという契約上の責任も負っています。したがって、発電事業者は収入への影響があるとしても、出力制御の要請に必ず対応しなければなりません。
出力制御の優先度
出力制御は太陽光発電のみを対象にしているわけではなく、すべての発電設備が対象となります。制御される順番は、優先給電ルールに基づき定められています。まずは火力発電や水力発電が第一に制御され、その後、必要に応じて太陽光発電や風力発電の制御が行われます。優先順位は以下の通りです。
| 優先順位 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 火力(石油、ガス、石炭)の出力制御、揚水・蓄電池の活用 |
| 2 | 他地域への送電(連系線) |
| 3 | バイオマスの出力制御 |
| 4 | 太陽光、風力の出力制御 |
| 5 | 長期固定電源※(水力、原子力、地熱)の出力制御 |
広がる太陽光発電の出力制御

太陽光発電の出力制御が全国に広がりつつあります。2021年度までは九州電力管内のみで実施されていましたが、2022年度からは他エリアでも制御が開始されました。同年には6社が新たに出力制御を行い、制御体制が大きく広がりました。さらに2023年度には3社が加わり、東京電力を除いた全国9社での出力制御が実施されています。2025年度には東京電力でも制御が予定され、10社すべてでの実施が見込まれています。
出力制御量が増大している主な要因は、太陽光発電の設備容量が急拡大しているためです。これにより、電力需要を上回る発電が起こりやすくなり、系統の安定供給を守るために出力制御が必要となります。特に晴天時や休日には電力需要が低く、過剰な電力が発生する傾向があります。これらの状況に対応するため、全国的に制御体制の整備が急務となっています。
再生可能エネルギーの導入拡大
東日本大震災後の原発事故や2020年のカーボンニュートラル宣言により、CO2削減への意識が一層強まり、再生可能エネルギーの導入が加速しました。さらに、昨今の電気料金高騰により、経済的な視点からも導入が進んでいます。政府は2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、電源構成における再生可能エネルギーの比率を、現状の約20%から36〜38%へ引き上げる方針です。
その結果、太陽光発電などの導入量は急増していますが、それに伴い、「出力制御」の必要性も高まっています。通常時は問題ありませんが、電力需要が少ない時期には発電量が消費を上回り、供給過多による制御が全国で行われるようになっています。特に太陽光発電は天候に左右されやすく、安定性に欠ける面も課題とされています。このように、再生可能エネルギーの拡大によって、出力制御を含めた新たな電力運用の工夫が求められています。
他地域への送電制限
出力制御には一定の優先順位が設けられており、最初に火力発電の出力を調整する対応が行われ、2番目に「他地域への送電」が行われます。太陽光や風力などの再生可能エネルギーは、制御の優先順位としては4番目になります。
以前は九州電力の管内に限定されていた太陽光発電の出力制御ですが、2023年度にはほぼすべての電力会社で実施されるようになってしまいました。つまり、電力を抑制したい場面が多く、他電力会社からの送電を受ける余裕がない状況です。
そのため、出力制御で2番目に優先される「他地域への送電」を行う余力がなくなってしまい、送電を通じて解消可能な電力量が減少してしまいました。その結果、4番目である太陽光発電や風力発電への出力制御がより頻繁に行われるようになってきています。
電力料金の高騰
ウクライナ情勢の影響により電気料金が高騰し、企業や家庭における節電の動きが広がっています。その結果、電力全体の需要が低下し、太陽光発電における出力制御の実施が増加しています。
出力制御の2025年度の見通し

2025年度、東京電力管内でも初めて出力制御が実施される予定です。これにより、全国10社すべてで出力制御が行われる見込みです。各地域の出力制御率はばらつきがあり、北海道が0.3%、東北2.2%、東京0.009%、中部0.4%、北陸2.1%などとなっています。最も高いのは九州で6.1%、最も低いのは沖縄の0.2%です。
出力制御量の予測では、北海道が0.20億kWh、東京は0.03億kWh、九州では10.4億kWhと、発電量や需給バランスにより地域差が明確です。2024年度と比較すると、北陸地方の制御率が大きく上昇しました。一方、九州は前年並みで、他地域は減少傾向を見せています。
全体として、2024年度におよそ24.2億kWhだった出力制御量は、2025年度には約20億kWhに減少すると見込まれています。これは、電力需給のバランスが改善していることを示す材料といえます。今後は、地域ごとの電力事情に応じた柔軟な出力制御の対応が必要になります。
このような変化に対して、発電事業者や関連企業は俊敏に対応することが求められます。市場の動向を的確に捉えながら、事業戦略や設備投資の再検討を進め、持続可能な供給体制の構築を図ることが重要です。
出力制御への対策

出力制御の仕組み、今後の見通しを理解いただいたところで、企業や家庭が取るべき出力制御への対策について、詳しく解説していきます。
出力制御への対策の他にも、FIT中期〜終盤に差し掛かる発電所オーナーの方にとっては、事業の継承、収支バランスの再検討など、それ以外にも対応すべき課題が一層増えてきます。こうした課題を整理し、これからの選択肢について『FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える』で解説しております。
オンライン制御の導入
出力制御に対応するためには、従来の方式では、発電事業者が自ら出力を停止する必要がありました。また、出力制御量を前日の午後4時までに確定する必要があるため、気象のずれに対応できず、実際には発電可能な状態であるにもかかわらず、停止せざるを得ないケースが多発しました。 一方、オンライン制御を導入すれば、遠隔操作で特定時間帯のみ自動制御が可能になり、柔軟な対応が実現します。出力制御量も発電の2時間前までに確定すればよく、急な天候の変化にも対応可能です。
実際、ある日に実施された出力制御では、午後1時30分の時点で自動制御が可能な設備では制御が行われなかった一方で、柔軟な対応が困難な設備では26万kWという大規模な制御が実施されました。このように、オンライン制御の導入は、より効率的で無駄のない電力運用に貢献すると期待されています。
FIP制度への移行
現行のFIT制度からFIP制度(Feed-in Premium)への移行が注目されています。FIP制度では、電力市場価格に応じたプレミアム収益が得られるため、収益性の向上が期待できます。特に蓄電池を活用することで、夜間など市場価格が高い時間帯に電力を売却でき、収益拡大が可能です。蓄電池の導入費用には、国の補助金が活用できます。需要家主導型太陽光発電や、再生可能エネルギー電源併設型蓄電池導入支援事業などがそれに該当し、初期投資の負担を軽減できます。
蓄電池の増設
蓄電池の増設が注目を集めています。中でも、北海道や九州では再生可能エネルギーによる発電量が大きく、電力需給のバランスを調整する手段として、蓄電池の活用が重要視されています。たとえば、電力需要が少ない時間帯に蓄電池へ電力を蓄え、需要が高まる時間帯に放電することで、供給の安定化を図ることが可能となります。この仕組みにより、余剰となった再生可能エネルギーを無駄にすることなく、効率的に活用する道が開かれます。
蓄電池の普及が進むことで、出力制御が求められるような状況下でも柔軟な電力調整が可能になり、より安定したエネルギー供給体制の構築に寄与します。持続可能なエネルギーシステムの形成には、蓄電池関連設備の整備が不可欠です。政府もこの流れを後押しするため、補助金制度の拡充を進め、企業や家庭における導入促進を図っています。さらに、技術革新に伴い蓄電池の性能向上やコストの低下が進んでおり、今後はいっそうの導入拡大が期待されます。
HEMS(ヘムス)の活用
住宅用太陽光発電においては、産業用に比べて出力制御の影響は限定的ですが、安定した運用のためには、一定の対策が欠かせません。その対策として特に有効なのが、HEMS(ヘムス)に組み込まれた蓄電池の活用です。HEMSとは、家庭用電力管理システムの一つで、電力使用状況をリアルタイムで可視化できるシステムです。日々の電力消費を効率的に管理し、節電にも大きく貢献します。また、HEMSを通じてエネルギーの使用や蓄電を自動制御することで、全体の電力運用を賢く行えるようになります。
現在では、大手住宅メーカーによる太陽光発電と蓄電池の連携によるスマートハウスの開発が進行中です。これにより、住宅内でのエネルギー管理が一層高度化し、将来的な電力需給の変動にも柔軟に対応できる住まいづくりが進められています。
ヒートポンプによる需要創出
従来、家庭用ヒートポンプは電気料金が安い夜間に蓄熱を行っていましたが、太陽光発電の増加により、近年では昼間の電力が安価になり、逆に夜間の電力が相対的に高くなっています。そのため、ヒートポンプによる蓄熱のタイミングを昼間にシフトすることで、昼間の余剰電力を有効活用でき、出力制御の抑制にも貢献できると期待されています。
出力制御の少ないエリアでの建設
出力制御は主に九州、中国、東北、四国の電力管内で多く発生しています。 そのため、太陽光発電の建設時にはこれらの地域を避けること自体も一つの対策です。 計画段階からの立地選定も重要です。
自家消費の推進
出力制御の影響を受けないという点で、完全自家消費型の太陽光発電は大きな優位性を持っています。外部の発電状況や電力需要の変動に左右されることなく、発電した電力を安定的に利用し続けられるため、計画的なエネルギー運用が可能となります。さらに、この仕組みは電力の自立性を高めるだけでなく、外部要因によるリスクを回避する手段としても有効です。電気料金の削減や環境への配慮という観点からも、自家消費は高く評価されています。
特に、再生可能エネルギーの比率が上昇し、電力需給のバランスが不安定になりつつある現在、需要側における調整力の強化はますます重要となっています。そのため、出力制御対策としての自家消費の推進は、今後さらに注目を集めることでしょう。
発電所の売却
特に九州地域では太陽光発電所の数が過剰となっており、2025年度も高水準で出力制御が継続される見通しです。このような出力制御の増加により、発電所の価値が下落する可能性も懸念されています。そのため、事業者は今後の市場動向を踏まえ、状況によっては適切なタイミングでの売却を検討することも求められます。
出力制御への対策【電力会社編】

これまでは、太陽光発電設備のオーナーが取るべき対策について解説してきました。ここからは、出力制御を行う側である電力会社が取り組んでいる、出力制御の機会を減らすための対策について解説していきます。
地域間連系線の活用
地域間連系線を活用することで、発電量が需要を上回る地域から、電力を必要とする地域へ効率的に送電することが可能です。例えば、九州で太陽光発電による余剰電力が発生した場合には、中部、中国、関西といった他地域へ送電することで、電力の全体運用が効率化されます。この取り組みにより、出力制御を行わずとも供給の安定が図られます。
火力発電の最低出力の引き下げ
出力制御への対策の一つとして、火力発電の最低出力を下げる取り組みがあります。現在、優先給電ルールにより、再生可能エネルギーよりも先に火力発電の出力調整が求められます。18社の火力発電事業者のうち、12社は定格出力の30%以下に引き下げることに同意しています。しかし、残る6社は技術的な理由で55~80%の間にとどまっており、柔軟な出力調整が難しい状況です
このため、太陽光や風力といった燃料費がかからない再生可能エネルギーの出力を制御せざるを得ません。燃料費が高く、二酸化炭素を排出する火力発電を優先するのは非効率的です。現状、最低出力の引き下げが難しい企業も、将来的には50%以下への低減を目指しています。公平性と効率性の観点から、再生可能エネルギーの出力制御を減らすには、最低出力を少なくとも50%に引き下げることが求められています。
デマンドレスポンスの推進
デマンドレスポンスは、電力需要のピーク時などに消費を抑制することで、需給のバランスを取る手法です。電力会社はこの取り組みを、安定供給と効率的な運用のために推進しています。主な手法として、「電気料金型」と「インセンティブ型」の二つがあります。
「電気料金型」では、需要が集中する時間帯の電気料金を引き上げます。これにより、消費者がその時間帯の使用を控えるようになります。この方式は広い範囲で導入しやすく、全体の使用量を減らす効果が期待されます。ただし、消費者の反応には差があり、成果に不確実性がある点が課題です。
一方、「インセンティブ型」では、電力会社が予め利用削減の要請を行い、それに応じた消費者に報酬を支払います。これにより、節電への動機づけが直接働くため、より効果の高い需要調整が可能です。この仕組みは需要予測の精度を高め、柔軟な電力管理を可能にします。電力会社はこれらの施策を導入・強化することで、持続可能なエネルギー社会の形成を目指しています。
まとめ
再生可能エネルギーの普及に伴い、出力制御の実施件数は全国的に増加傾向にあります。2023年度には、実に18億kWhもの電力量が出力制御によって抑制され、発電事業者の売電収入に大きな影響を及ぼしました。特に、九州電力の管内では実施頻度が高く、2025年度は東京電力を含む全国10社で実施される見込みです。
こうした状況を受け、オンライン制御の導入やFIP制度への移行が有効な対策として挙げられます。また、余剰電力を有効に活用する手段として、蓄電池の導入にも関心が集まっています。あわせて、自家消費の推進やHEMSの活用も、有効な手段のひとつといえます。さらに、発電所の立地や売却のタイミングは、収益性を左右する重要な戦略要素です。
制度対応の義務を正しく理解した上で、需給バランスの維持に貢献していく姿勢が求められます。市場や制度が変動する中、柔軟に対応して、早期に適切な対策を講じていきましょう。最後までお読み頂き誠にありがとうございます。
オムロン ソーシアルソリューションズでは、出力制御への対策以外にも注目すべき、FIT制度の終了を見据えた収支計画の見直しや、機器の更新や廃棄、さらには事業承継に役立つ情報を提供しています。本記事よりも実践的で有益な情報が満載です。収益性の向上を目指す方は、ぜひダウンロードしてご一読ください。