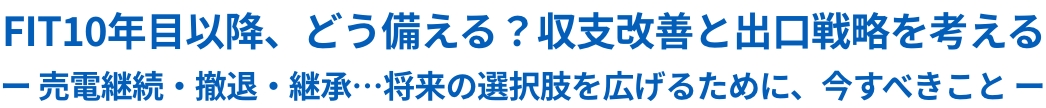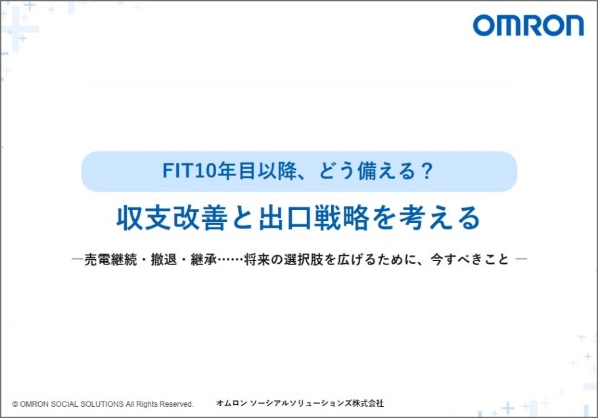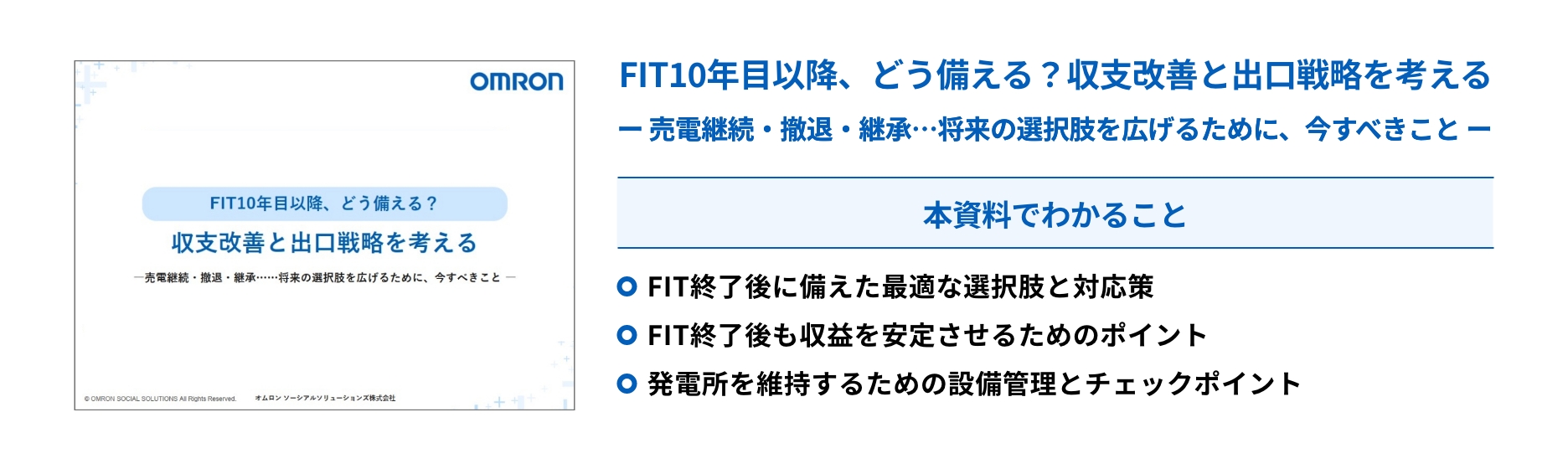【太陽光売電】11年目以降おすすめの運用方法5選|売電価格の低下に備える

2012年に始まったFIT制度(固定価格買取制度)により、太陽光発電の売電は多くの家庭や企業にとって魅力的な選択肢となりました。導入から10年間(産業用は20年)は電力会社が固定価格で電気を買い取るため、安定した収入が見込めます。しかし、この制度は一定期間で終了します。早い場合、11年目以降は「卒FIT」の課題に直面します。卒FITでは買取価格が下がることが一般的で、売電による収益の減少が避けられません。そこで本記事では、FIT制度の基本から、卒FITを迎えた後でも経済的なメリットを保つための具体的な運用方法を5つ紹介します。制度終了後も太陽光発電を有益に活用するためのポイントをお届けします。
目次
太陽光の売電制度「FIT」とは?

FIT制度とは、国が定めた固定の価格で再生可能エネルギーによる電力を一定期間買い取る仕組みであり、太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入促進を目的としています。通常の市場価格よりも高い価格で電力を買い取ってくれることで、太陽光発電の導入を後押ししてきました。
制度の適用条件は発電設備の規模によって異なります。住宅用で10kW未満の小規模発電は、10年間にわたって余剰電力のみが買い取られます。一方、産業用として10kW以上の中・大規模発電は、20年間にわたり発電した全量が対象となります。ただし、現在では状況に応じて余剰買取やFIP制度(Feed-in Premium)が適用される場合もあります。
なお、FIT制度の適用期間が終了すると「卒FIT」となり、それまでの固定価格による買取は継続できなくなります。この制度は再生可能エネルギーの普及や発電設備の増加に大きく貢献しており、今後も持続可能なエネルギー社会の実現に向けた重要な役割を担っています。
産業用の場合、11年目以降に取るべき対策とは?
産業用(10kW以上)の場合、FIT制度では、20年間にわたって発電電力の全量を電力会社が買い取る仕組みとなっています。これにより、事業者は長期間にわたって安定した収益を見込むことが可能です。ただし、制度利用から10年ほど経過すると、注意すべき点が出てきます。
それは、パワーコンディショナー(以下、パワコン)の寿命です。多くのメーカーは標準保証期間を10年程度と設定しており、それ以降は部品の劣化や故障のリスクが高まります。パワコンが故障したまま放置すると、発電効率が大幅に低下し、固定単価での売電であっても収入が目減りしてしまう恐れがあります。そのため、タイミングを見極めてパワコンの交換や性能を高めるリパワリングを行うことが大切です。初期投資は必要ですが、発電量が回復すれば売電収入が向上し、長期的なメンテナンスコストも削減できる可能性が高いといえます。
FIT終了後の売電価格が大幅に下がる理由
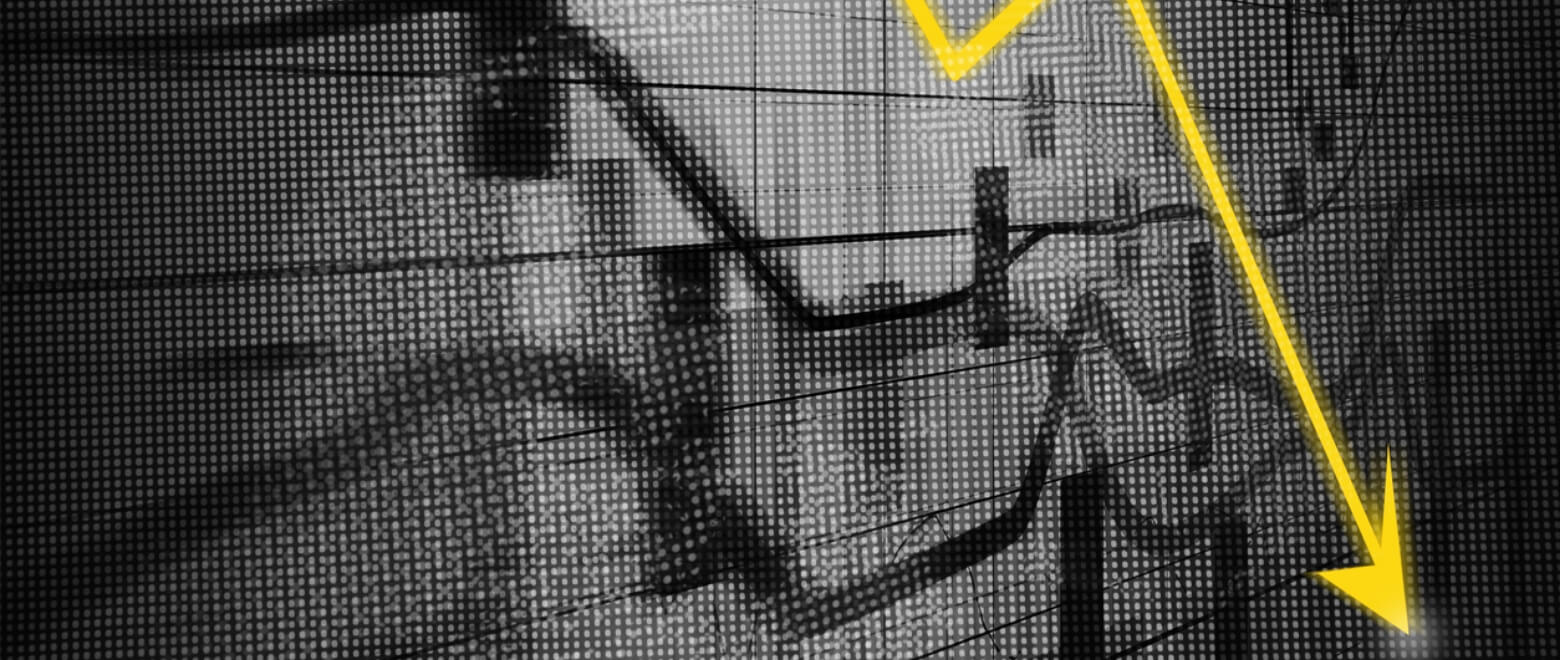
FITでは、太陽光発電による電力を国が定めた価格で買い取ってくれます。2024年度の住宅用(10kW未満)の買取価格は1kWhあたり16円、2025年度は15円です。この期間は売電価格が安定し、投資の見通しも立てやすいのが特徴です。しかし、FIT期間は10年間で終了します。これ以降は「卒FIT」と呼ばれ、自由市場での取引になります。
卒FIT後の売電価格はFIT時の約6割まで下がります。例えば、東京電力の卒FITプランでは8.5円/kWhです。つまり、売電による収入はほぼ半額になります。太陽光設備の設計寿命は、太陽光パネルが20〜30年、パワコンは10〜15年です。そのため、卒FIT後も発電自体は継続できますが、得られる収益は大きく下がります。
設置費用は10年程度で回収できるケースが多いですが、卒FIT後の収入減を見込んだ上で長期的な運用計画が必要です。家庭内での自家消費や蓄電システムの活用など、今後の戦略を早めに検討することが求められます。
FIT終了後の売電価格
太陽光発電のFIT制度が終了した後の売電価格は、FIT期間中に比べ、大幅に下がるのが一般的です。例えば、2014年度には1kWhあたり37円で買取されていたものが、卒FITの11年目以降には北海道電力の場合で約1/5となる8円にまで落ち込むと見込まれています。実際に卒FIT後の買取価格は地域や電力会社によって異なり、東京電力は8.5円、中部電力7円、北陸電力8円、四国電力7円、中国電力7.15円、関西電力8円、九州電力7円、北海道電力8円、東北電力9円と設定されています。
このような価格低下の背景には、電力の需給バランスが関係しており、時期や地域における電力需要によっては、さらに価格が下落する可能性もあります。こうした状況では、売電収入の減少が避けられず、従来のように売電のみで経済的メリットを得ることは難しくなります。そのため、今後はFIT制度終了後の市場価格動向を見極めたうえで、適切な対策を講じる必要があります。経済的なメリットを維持するには、売電価格の下落に対応できる新たなビジネスモデルや、蓄電技術などの革新を導入することが重要となるでしょう。
大手電力会社とその他事業者の卒FIT買取価格の比較(2025年4月時点)
FIT制度の適用期間が終了すると、売電価格は大幅に低下します。つまり、11年目以降の売電契約については、改めて条件を見直す必要があります。大手電力会社の価格と合わせて、一例として、エネオスと伊藤忠エネクスの価格を紹介します。2025年4月時点における卒FIT家庭向けの買取価格は、以下の通りです。
| 電力エリア | エネオス | 伊藤忠エネクス | 電力エリア 大手電力会社 |
|---|---|---|---|
| 北海道エリア | 11円 | 11円 | 8円 |
| 東北エリア | 11円 | 10円 | 9円 |
| 東京エリア | 11円 | 12.5円 | 8.5円 |
| 中部エリア | 10円 | 10.5円 | 7円 |
| 北陸エリア | 10円 | 8.5円 | 8円 |
| 関西エリア | 10円 | 10円 | 8円 |
| 中国エリア | 10円 | 10円 | 7.15円 |
| 四国エリア | 10円 | 8.5円 | 7円 |
| 九州エリア | 7.5円 | 7.1円 | 7円 |
参考)太陽光電力買取サービス
このように、各社の買取価格には地域ごとの差があります。電力会社によっても最大で3円程度の差があることがあります。より高い価格で売電するには、契約先の比較と選定が必要です。信頼性やサービス内容にも注目し、最適な運用を行いましょう。
11年目以降におすすめの「リパワリング」

リパワリングとは、太陽光発電設備の各種機器をアップグレードまたは交換することで発電能力を向上させるプロセスを指します。中でも発電効率に直結するパワコンの交換は、特に経済的効果が大きいとされています。2012年にFIT制度が始まった当初、パワコンの変換効率は約90%でしたが、現在では93%〜95%へと改良が進んでいます。
仮に90%のパワコンを95%のパワコンに取り替えた場合、理論的には売電収入が約5%増加します。年間発電量が50万kWhであれば、2.5万kWhの増加が見込まれ、これを2015年度のFIT制度(10kW以上)の売電価格である29円で換算すると、年間で72.5万円の収入増となります。このように、10年以上稼働した太陽光発電所においては、リパワリングは発電効率の改善とともに収益性を向上させる有効な手段と言えるでしょう。
太陽光発電システムは経年劣化する
太陽光発電システムは、使用年数の経過とともに発電効率が徐々に低下していきます。太陽光パネルの寿命は一般に20〜30年とされていますが、時間の経過に伴い、ガラス部分の変色や破損などの劣化が確認されるケースもあります。また、配線の腐食や半導体の性能低下により、年間でおおよそ0.25%〜1%の発電効率低下が生じるとされています。
さらに、電力変換を担うパワコンについては、10〜15年での交換が必要とされており、こうした要因が売電収入に与える影響も無視できません。しかし、11年目以降に「リパワリング」を実施することで、システム全体の性能維持が可能となります。これは設備の信頼性および発電量の回復に影響して、長期的な収益の確保につながります。
太陽光発電の技術進歩が進んでいる
太陽光発電設備の設置から11年目以降を迎えると、最新技術への更新で効率向上が見込める「リパワリング」が有効な選択肢となります。近年では、太陽光パネルや関連機器に組み込まれる半導体技術が進化し、電気への変換効率が向上しています。従来の太陽光パネルでは15%〜18%の発電効率でしたが、現在では20%を超える高効率モデルも登場しています。また、パワコンも変換効率の向上とともに、小型化が進んでいます。
さらに、電力の流れを制御しながら内部温度をリアルタイムで監視する熱暴走防止機能を持つ機器や、各太陽光パネルの発電量を個別モニタリングし最適化するオプティマイザーを備えた製品も開発されています。こうした技術革新により、発電効率の改善だけではなく、長期的なメンテナンスやコストの削減にもつながることが期待されます。
FIT認定が早い設備ほど、リパワリングの効果を期待できる
リパワリングはFITの認定時期によって効果が異なります。売電単価は年々低下していますので、売電単価が高かった頃に認定を受けた設備ほど、リパワリングによる収益効果は高いと期待できます。単なる機器交換ではなく、投資回収の視点から見て効果的な提案ができる実績ある業者に相談しましょう。収益性を高めるには、事前のシミュレーションが不可欠です。
11年目以降、おすすめの運用方法5選

11年目以降のおすすめ運用方法5選を解説します。今後の運用方針を検討するうえで、一定の指針にしていただけると幸いです。
自家消費の拡大
11年目以降は、FIT制度の期間終了に伴い売電収入が減少するため、経済的メリットを最大化するには自家消費の拡大が重要となります。近年は燃料調達費の上昇や電気代の高騰が続いています。太陽光発電で得られた電力を自社の事務所や自宅で使用することで電気代のコストを大幅に削減でき、毎月の支出を抑えることが可能です。なお、太陽光発電の導入時にはFIT制度の適用期間中か終了後かを問わず、電力会社への売電のみに頼るよりも、自家消費に重きを置く方が長期的に見て経済的に有利である可能性もあります。
蓄電池を導入する
卒FITを迎えた11年目以降、太陽光発電の経済的な活用には、自家消費比率の向上が不可欠です。その際、家庭用蓄電池の導入は有効な手段の一つと言えます。蓄電池があれば、日中に発電した電力を貯め、夜間や天候の悪いときに利用することが可能となります。太陽光パネルのみでは、電力の自給率はおおよそ30〜40%にとどまりますが、蓄電池を併用することで、70〜80%以上をカバーできるケースもあります。
その結果、電力購入量を大幅に削減でき、光熱費の低減につながります。蓄電池本体の価格は、5kWhでおよそ70万円、6kWhが84万円、7kWhでは98万円と、容量に応じて異なります。卒FIT以降を見据えた電力運用においては、蓄電池の導入について早めに検討を始めることが賢明です。
非常用電源としても活躍
蓄電池のほかのメリットをご紹介します。蓄電池があれば、万が一停電が発生した場合でも電力を確保することが可能です。さらに、非常用電源としても安心です。日本は地震や台風など自然災害が多く、蓄電池の需要は高まっています。容量や家族構成により異なりますが、2〜4日分の最低限の電力供給が可能です。信頼性と安心を得る運用方法の一つです。
補助金の活用
蓄電池に興味はあるものの、初期費用の高さから導入に踏み切れない人も少なくありません。こうした課題に対応するため、国や自治体では一般向けの補助金を設け、購入を促進しています。ただし、これらの補助金には予算上限が設けられており、予定額に達すると申請期間前であっても受付が終了することがあるため、早めの手続きが重要となります。
理想的には、補助金の申請開始前から見積もりを準備し、開始日当日に申し込みを行う位のスピード感が望ましいです。詳細については地域ごとに異なるため、自治体のホームページなどで最新の情報を確認して進めていきましょう。
そのまま売電を続ける
太陽光発電の11年目以降は、既存の電力会社と売電契約を続ける選択肢があります。契約期間終了後も、特別な手続きは不要で自動的に継続されます。ただし、複数のプランが用意されているため、内容をよく比較しましょう。価格はFIT制度より低くなりますが、売電先を新たに探す必要がない点がメリットです。手軽さを最優先する方には有効な方法です。卒FIT後も安定収入を得る一手として検討する価値があります。
新たな売電契約を結ぶ
新たな売電契約を結ぶ方法もあります。買取価格はFIT期間中に比べて低くなりがちですが、複数の電力会社のプランを比較し、なるべく高い買取価格で契約を結ぶことで、収入減の影響を低く抑えられる可能性があります。中でも大手電力会社との契約は手続きが簡易で、サービス内容によっては電気料金を削減する効果も期待できます。
一方で、新電力会社は大手より高い買取価格を提示することがあり、高額な売電を目指す場合には有力な選択肢となります。ただし、新電力会社には買取価格が定期的に見直されることや、事業継続に不安があるなどのデメリットも存在するため注意が必要です。さらに、市場全体の価格動向によっては買取価格が下がり、継続的な収入が不安定になるリスクも伴います。
オフサイトPPAの活用
「オフサイトPPA(電力購入契約)」は主に法人向けの仕組みであり、太陽光発電所が生産した電力を、需要家である企業などに直接供給するモデルです。オフサイトPPAは、長期にわたる売電契約が可能なことから、発電事業者にとっては継続的かつ安定的な収益源となる点でメリットがあります。加えて、電力市場における価格変動によるリスクを一定程度抑えることが可能であるため、収益計画の策定・遂行においても優位性があります。特に、FIT終了後の売電契約先が定まっていない発電事業者にとっては、現実的かつ有効な選択肢になると考えられます。
電力を購入する企業側も、一般的な電力会社から購入するよりも安価に電力を調達でき、コスト削減と同時に環境配慮を実現できます。二酸化炭素の排出削減にもつながるため、企業のESG(環境・社会・ガバナンス)対策としても有効です。FIT終了後の運用を見直す中で、オフサイトPPAは今後さらに活用が広がると考えられています。
FIT中期〜終盤に差し掛かる発電所オーナーの方にとっては、事業の継承、収支バランスの再検討など、それ以外にも対応すべき課題が一層増えてきます。こうした課題を整理し、これからの選択肢について『FIT10年目以降、どう備える?収支改善と出口戦略を考える』で解説しております。
太陽光発電のメンテナンス・点検の重要性

太陽光発電システムを長期間にわたって安定的かつ効率的に運用するためには、定期的なメンテナンスと点検が不可欠です。特に、10年以上運用されているシステムは、経年劣化や汚れの蓄積などの影響を受けやすくなってきますので、定期的な対応が極めて重要となります。長期の使用により、太陽光パネル表面には汚れが蓄積しやすく、それが太陽光の吸収効率の低下を招く可能性があります。このため、定期的な清掃を通じて、発電量の減少を最小限に抑えることが求められます。
インバーターや接続部、ケーブルといった関連機器も年数の経過とともに劣化が進行します。こうした劣化が続けば、出力の低下やシステム全体の故障につながるリスクが高まります。定期点検を実施することで不具合を早期に察知し、大きなトラブルを未然に防ぐことが可能です。
メンテナンスを怠った場合、電気火災や太陽光パネルの飛散といった深刻な事故に発展する恐れもあります。こうしたリスクを抑えるためには、日常的な設備確認に加え、必要に応じた補修・補強が重要となります。さらに、地震や台風といった自然災害への対応として、機器の固定具や配線の安全性を点検して、適切な対処を講じることが求められます。
なお、2017年のFIT法改正によって、太陽光発電システムに対する定期点検およびメンテナンスの実施が法的に義務付けられています。この義務を怠った場合には、罰則が科されることもあるため、対応には十分な注意が必要です。
まとめ
FIT制度の終了後、太陽光発電オーナーが直面する最大の課題は、売電単価の大幅な下落です。特に住宅用(10kW未満)の場合は制度の適用期間が10年と短いため、制度終了後にも収益性を確保する手段を早くから考えておく必要があります。
まず検討したいのが、新たな売電契約の締結です。卒FITユーザー向けに、比較的高い買取価格を提示する新電力会社がでてきています。複数社のプランをしっかりと比較検討して、自身・自社の発電状況と照らし合わせ、最適な契約先を選定しましょう。その他には、オフサイトPPA(電力購入契約)が注目されています。これは、企業や施設へ直接電力を販売する仕組みであり、長期的かつ安定した収入源として注目されています。
一方、産業用(10kW以上)の場合は20年間の固定買取期間が設けられていますが、注意すべき点があります。それはパワコンの寿命です。一般的に約10年とされており、故障や劣化を放置すると、発電量が大幅に低下します。適切なタイミングでリパワリングを行い、売電収入の改善・向上を図ることが求められます。
最後までお読み頂き誠にありがとうございます。
オムロン ソーシアルソリューションズでは、太陽光発電所の所有者に向けて、FIT制度の終了を見据えた収支計画の見直しや、機器の更新や廃棄、さらには事業承継に役立つ情報を提供しています。本記事よりも実践的で有益な情報が満載です。収益性の向上を目指す方は、ぜひダウンロードしてご一読ください。