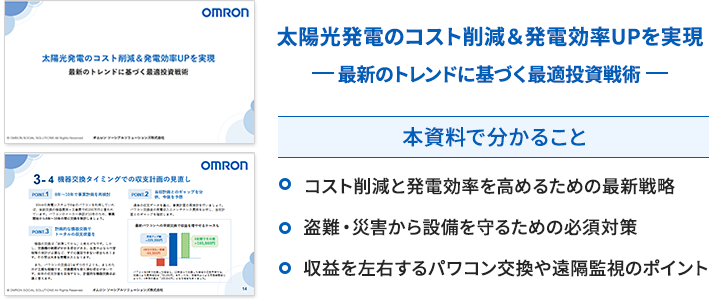太陽光発電の効率とは?発電効率と変換効率の違いから、効率の高め方まで解説

太陽光発電は、二酸化炭素を排出しないクリーンなエネルギーとして注目されています。一方で、他の再生可能エネルギーと比較すると、発電効率が高くないと思われる方もいるかもしれません。発電効率、そして変換効率とは、太陽光をどの程度電力に変換できるかを示す割合(%)を指します。現在流通している太陽光パネルの一般的な変換効率は15%〜20%ですが、変換効率が20%を超える高性能なモジュールも登場しており、技術の進歩により効率は向上しています。この記事では、太陽光発電の効率に関する基礎知識から、効率が下がってしまう要因や改善方法まで解説します。
目次
太陽光発電の効率とは?

太陽光発電の効率を説明する際は、「発電効率」と「変換効率」の2種類を区別する必要があります。火力発電のように、石油や石炭、天然ガスなどの燃料を必要とする発電における「発電効率」とは、燃料エネルギーのうち、電気に変換された割合を表します。一方、燃料を必要としない太陽光発電においては、太陽光エネルギーのうち、電気に変換された割合を表します。太陽光パネルを利用することで、燃料を必要とすることなく、太陽光エネルギーを直接、電気に変換することができるのです。
一方、「変換効率」は、太陽光パネルが太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する効率を示す割合です。太陽光パネルの出力と変換効率は、季節や温度、日射の強度、太陽光パネルの角度など複数の条件に依存します。そのため、カタログなどでは、世界共通の一定条件下で測定した変換効率が記載されています。
太陽光発電の発電効率が低下してしまう原因

太陽光発電システムの発電効率が低下する原因について、詳しく解説します。発電効率の低下は、太陽光発電事業者にとって大きな課題となっています。本記事では、その原因を明らかにし、対策を検討するための情報を提供します。
天候による変動
太陽光発電システムの発電効率は、天候の影響を大きく受けます。曇りや霧の多い日、また太陽高度が低い朝夕の時間帯では、日射量の減少により発電量が低下する傾向にあります。一方、晴天時には、発電量は通常の水準に回復するのが一般的です。しかし、晴れた日にもかかわらず発電効率が改善されない場合は、太陽光パネルやシステムに何らかの不具合が生じている可能性があるため、速やかに点検を実施することが重要です。
長期運用による経年劣化
太陽光パネルは、経年劣化により発電効率が低下します。一般的な劣化率は年間0.3%から0.8%程度であり、最大で約1%と見積もられています。太陽光発電協会の観測では、1年間での劣化率は0.27%とされる一方、農林水産省の報告では0.5%の劣化が示されています。
出典)
一般社団法人 太陽光発電協会|太陽光発電システムの調達価格、期間への要望
水産庁|漁港のエコ化方針(再エネ)ガイドライン
太陽光パネルの寿命は20年以上と設定されていますが、長期的なデータに基づく具体的な劣化の観察は十分ではありません。今後、さらなる研究とデータの蓄積が求められます。太陽光発電の普及拡大に向けては、経年劣化対策と発電効率の維持が重要な課題となっています。
建物や樹木の影の影響
太陽光パネルの発電効率を最大限に引き出すには、太陽光が直接太陽光パネルに届くことが極めて重要です。したがって、建物や樹木、電信柱、アンテナなどの障害物による影の影響を最小限に抑えるため、最適な設置場所の選定が求められます。また、遠方の山や森林なども、季節によっては影を落とす可能性があります。特に冬場は影が長くなる傾向があるため、季節変動も考慮する必要があります。
以上を踏まえ、太陽光パネルの設置計画では、将来的に影響を及ぼし得る周囲の植栽や建築物の計画も視野に入れ、影の影響が最小限となるよう立案することが重要です。
外気温による性能低下
太陽光パネルの発電効率は、外気温に大きく依存します。最適な太陽光パネルの表面温度は25℃とされており、この温度の時に性能が最も高くなります。しかし、気温が上昇すると太陽光パネル表面の温度も上がり、25℃を超えると、1℃上がる毎に発電効率が約0.5%ずつ低下することが知られています。これは、高温になると太陽光パネルの電圧が低下し、その結果、発電量も減少するためです。
特に日射量が多く日の長い夏の季節には、外気温が高いことで太陽光パネルの温度が70〜80℃にも達することがあり、発電効率の低下が顕著になります。そのため、太陽光パネルの設置場所選びは、日当たりだけでなく、温度の上昇が抑えられる環境を考慮することが重要です。
国際規格では、性能評価の基準として太陽光パネルの表面温度を25℃と定めており、メーカーが公表するスペックもこの条件下で示されています。実際の発電量を予測する際には、設置場所の気象条件を考慮し、温度上昇による効率低下を見込んでおく必要があります。
メンテナンス不足による汚れや損傷
太陽光パネルは屋外に設置されるため、外的要因による発電効率の低下が起こり得ます。鳥の糞や黄砂、花粉、落ち葉などの汚れが太陽光パネル表面に蓄積すると、太陽光の吸収が妨げられ、発電量が減少します。また、強風で飛来した物体による太陽光パネルの損傷も、特に自然災害時には注意が必要です。
これらの問題を防ぐには、定期的なメンテナンスが不可欠です。清掃の頻度は設置環境により異なりますが、専門業者に相談し、適切なメンテナンス計画を立てることが重要です。適切な管理によって、太陽光パネルは最適な状態を維持し、発電効率の低下を最小限に抑えられます。
太陽光発電の発電効率を高めるには?

太陽光発電システムの発電効率向上について解説します。太陽光パネルの設置角度や設置場所を最適化することで、発電量を増加させることが可能です。詳しく解説していきます。
太陽光パネルに最適な設置環境
太陽光パネルの発電効率は、設置条件によって大きく左右されます。主要な設置条件には、日射量、太陽光パネルの方位や向き、設置角度、温度、表面の汚れなどが挙げられます。まず、日射量は太陽の放射エネルギー量を示します。地域によって異なり、西日本の太平洋側や内陸部では日射量が多い一方、北海道や東北、日本海側では相対的に少ない傾向にあります。次に、効率的な発電のためには、太陽光パネルの方位を真南に向けることが理想的です。南方向への設置が難しい場合は、南東や南西、さらには東や西への設置が検討されます。
また、太陽光パネルの最適な設置角度は30度とされており、これにより太陽光を効率的に受けることができます。すべての条件を完璧に満たすことは難しい場合もありますが、可能な限り最適な条件下で発電を行えるよう努力することが重要です。
環境に適した太陽光発電システムの選択
太陽光発電の効率向上には、設置環境に適したシステムの選定が欠かせません。特に環境の影響を受けやすい地域では、専用に設計されたシステムの採用が重要です。例えば、積雪量の多い地域では、耐雪性能の高い太陽光パネルを選ぶことで、積雪による破損リスクを回避できます。海沿いの場所では、塩害対策として耐塩性の高い太陽光パネルを設置し、パワーコンディショナー(パワコン)や蓄電システムは塩分の影響を受けにくい屋内に設置するのが効果的です。
また、台風の頻発地域では、耐風性の高い太陽光パネルを選択することで、強風による損傷リスクを低減し、発電効率の維持が可能となります。このように、周辺環境の特性に合わせた太陽光発電システムの選定が発電効率の向上には不可欠です。適切なシステムの導入により長期的に安定した発電が実現し、再生可能エネルギーの有効活用につながります。
発電データの記録と分析
太陽光発電システムの発電効率向上には、計測モニターの活用も有効です。日々の発電量を記録し、過去データと比較・分析することで、変化をいち早く察知できます。ただし、発電量は外部環境の影響を受けるため、同一条件下でのデータ比較が重要となります。より精度の高い分析のためには、日付や時間、天候などの情報も併せて記録し、適正値との比較が必要不可欠です。計測モニターの設置は義務ではありませんが、可能な限り導入することをおすすめします。これらの手法を用いることで、太陽光発電システムの発電効率を高め、安定的な電力供給の実現が可能となるのです。
リパワリングの活用
太陽光発電システムの発電効率を高めるためには、太陽光パネルの設置条件に加え、太陽光パネル自体の品質も重要な要素となります。高い変換効率を持つ太陽光パネルを選択することで、同じ設置条件下でも発電量の向上が期待できます。さらに、パワコンの性能も発電効率に大きく影響します。変換効率の高いパワコンを使用することは、太陽光発電の効率を間接的に高めることにつながるでしょう。
ただし、高品質な太陽光パネルやパワコンを導入しても、経年劣化による効率の低下は避けられません。そこで、定期的なリパワリングが重要となります。リパワリングとは、老朽化した機器を最新の製品に交換する手法です。太陽光パネルとパワコンの効率は、技術進歩に伴い年々向上しており、市場には常に高性能な製品が登場しています。これらの製品への交換により、太陽光発電の発電効率を高めることが可能です。一般的に、パワコン交換によるリパワリングは、設置から10年が経過した時点で検討すると良いでしょう。
太陽光発電事業の収益を安定して確保するためのポイントについては、『太陽光発電のコスト削減&発電効率UPを実現 最新のトレンドに基づく最適投資戦術』という資料で詳しく解説しています。
太陽光発電の変換効率について

太陽光発電の変換効率について、より専門的な解説をいたします。変換効率は「モジュール変換効率」と「セル変換効率」の2種類の指標で表され、太陽光パネルの性能を示します。モジュール変換効率は太陽光パネルの全体性能を、セル変換効率は太陽光パネルを構成する個々の太陽電池の性能をそれぞれ表しています。
これらの指標は、太陽光エネルギーがどれだけ効率的に電気エネルギーに変換されるかを測定することで、太陽光発電の効率を評価します。つまり、太陽光パネルの枚数が同じでも、変換効率が高い太陽光パネルはより多くの電力を発電できるのです。
モジュール変換効率
モジュール変換効率とは、太陽光パネルが1平方メートルあたりどれだけのエネルギーを電気に変換できるかを示す重要な指標です。ここでいう「モジュール」は「太陽光パネル」と同義で使用されています。太陽光パネルには「有機系」「化合物系(CIS太陽電池)」「シリコン系」の3種類があり、それぞれ変換効率が異なります。有機系は約8%、化合物系は約14%〜15%、シリコン系は約15%〜20%の効率が一般的とされています。現在、一般に販売されている太陽光パネルのほとんどは「シリコン系」であるため、購入できる太陽光パネルの変換効率は、通常15〜20%程度となります。なお、シリコン系の変換効率の理論的限界は約29%とされています。
セル変換効率
セルとは、太陽光パネルを構成する太陽電池の基本単位であり、セル変換効率はこれら太陽電池1枚あたりの変換効率を示します。セル変換効率の計算式は次の通りです。
セル変換効率(%)=[モジュール公称最大出力(W)× 100]÷[1セルの全面積(m²)×モジュール内のセル数(個)× 放射照度(W/㎡)]
※(放射照度=1,000W/m²)
セル変換効率が高いほど、より多くの電気エネルギーを発電できるため、この効率の高さは非常に重要な指標とされています。また、セル変換効率は電気抵抗の影響を受けずに測定されるため、一般的にモジュール変換効率よりも数値が高めに出ることが多いです。ただし、中にはセル変換効率を意図的に高く見せかけている場合があるため、消費者は注意が必要です。セル変換効率は太陽光パネル全体の性能を示すものではないことを理解し、モジュール変換効率など他の指標も総合的に判断することが大切です。
技術開発が進む変換効率
太陽光発電の世界全体での設備容量は1TWを超え、全発電量の約5%を占めるまでに拡大しています。太陽光パネルは継続的に進化を遂げており、変換効率も年々向上しつつあります。最も普及しているのは「シリコン系」であり、中でも「結晶シリコン」が材料として使用されるケースが増えています。一般的なシリコン系の変換効率は15%〜20%ですが、世界最高性能の結晶シリコン型では26.6%に達しています。また、日本発の材料「ペロブスカイト」との組み合わせにより、32%を超える効率を実現する太陽光パネルも開発されつつあります。さらに、宇宙用の「多接合型」では、40%近い変換効率を有するものも存在しています。今後も技術開発が進展することで、太陽光パネルの効率向上が期待できます。
太陽光発電の発電効率について

発電効率とは、投入したエネルギーがどの程度の割合で電気に変換されるかを示す指標です。特に太陽光発電の場合、太陽エネルギーを効率的に電気エネルギーに変換することが非常に重要となります。効率が高いほどエネルギーロスが減少するため、発電効率の向上は太陽光発電システムの性能を大きく左右します。一般的に、太陽光発電の平均的な発電効率は約20%であると言われています。つまり、太陽光エネルギーの20%が電気エネルギーに変換され、残りの80%は熱などの形で損失しているのです。今後の技術革新により、発電効率のさらなる向上が期待されています。
メーカーによる発電効率の違い
太陽光パネルの発電効率は、メーカーによって大きく異なります。各社が有する技術力が、発電効率の違いを生み出しているのです。各メーカーの発電効率は、プレスリリースを通じて公開されるデータから知ることができます。特に高い効率を誇るのは、パナソニック、Qセルズ、カナディアンソーラーなどです。これらのメーカーは、独自の技術を駆使し、効率向上と技術革新を継続的に推し進めています。消費者にとっては、これらの情報を参考にしながら、自身のニーズに最適な太陽光パネルを選択することが求められます。
その他の再生可能エネルギーとの効率の比較

太陽光発電の発電効率は現在約20%です。他の再生可能エネルギーでは、次の表のようになっています。
| 発電方法 | 発電効率(目安) | 発電コスト(kWhあたり) ※2020年の試算 |
|---|---|---|
| 太陽光発電 | 約20% | 産業用太陽光発電:12.9円 住宅用太陽光発電:17.7円 |
| 水力発電 | 約80% | 中規模水力発電:10.9円 小規模水力発電:25.3円 |
| 風力発電 | 約40% | 陸上風力発電:19.8円 洋上風力発電:30.0円 |
| バイオマス発電 | 約20~35% | バイオマス混焼(5%):13.2円 バイオマス専焼:29.8円 |
| 地熱発電 | 約8% | 16.7円 |
| 【参考】火力発電 | 約40〜50% | 石炭火力発電:12.5円 LNG火力発電:10.7円 石油火力発電:26.7円 |
出典)
資源エネルギー庁|電気をつくるには、どんなコストがかかる?「2020年の電源別発電コスト試算結果」
資源エネルギー庁|火力発電の高効率化
エネルギーのまち 能代|自然エネルギーの発電効率を比較してみた
三井物産|バイオマス発電とは?仕組みメリットを分かりやすく解説
このデータから、太陽光発電の効率は特別高いわけではありませんが、発電効率だけで各発電方法の優劣を判断するのは不十分だと言えます。太陽光発電のコストは12.9円から17.7円程度であり、他の多くの再生可能エネルギーと比べて低コストです。
水力発電は10.9円から25.3円のコストで運用されており、コストパフォーマンスが高い一方、設置場所や環境による制約が大きいのが特徴です。地熱発電のコストは16.7円、バイオマス発電は13.2円から29.8円、風力発電は19.8円から30.0円とされています。
つまり、発電効率だけでなく、コストや環境影響を含む多角的な視点から各発電方式の適用可能性を検討する必要があるのです。続いて、各再生可能エネルギーについて詳しく解説します。
水力発電の効率
水力発電は、水の流れや高低差を利用して位置エネルギーを電気エネルギーに変換する発電方式であり、その効率は約80%に達します。これは他の再生可能エネルギー源と比較しても最高水準の効率といえます。しかし、降水量の変動によって発電量が制限されることがあり、特に乾期には水量減少に伴い発電量が低下する課題があります。
水力発電のコストは、発電所の規模や設計によって異なり、10.9円から25.3円/kWhの範囲で変動します。大規模な設備ではダムを活用することで規模の経済が実現でき、コスト削減が可能です。ただし、その効率は依然として環境条件の影響を受けるのが現状です。
風力発電の効率
風力発電は、風の運動エネルギーを利用して風車とタービンを回転させ、電力を発電する再生可能エネルギーの一つです。理論上の最大発電効率は約60%ですが、風車の摩擦などにより、実際の効率は40%程度に低下します。また、風の有無および強さに左右されるため、発電量は不安定であり、安定供給の実現が課題となっています。
風力発電のコストは、地形や設置場所によって異なります。陸上風力の場合は約19.8円/kWh、洋上風力の場合は約30.0円/kWhであるため、地域によって経済性に大きな差があるのが特徴です。再生可能エネルギーの中では、風力発電は比較的効率が良い部類に入りますが、風車の設置には広大な土地の確保と、周辺地域への景観や騒音影響への配慮が必要不可欠です。
バイオマス発電の効率
バイオマス発電は、木質バイオマスをはじめとする動植物由来の資源を利用して電力を発電する方法です。主な燃料となるのは植物の廃棄物や動物のふん尿などの生物資源であり、これらを燃焼またはガス化することで発電を行います。木質バイオマスの場合、燃料として利用されるのは主に廃材や残材ですが、化石燃料と比較すると燃焼温度が低いため、平均発電効率は約20%程度と低めにとどまっています。
バイオマス発電全体の効率は約20%から35%の範囲であり、発電コストも燃料費の高さなどにより13.2円から29.8円と幅広く変動します。特に、燃料費の高さがバイオマス発電のコストを押し上げる主要因の一つであり、最大の課題となっています。
地熱発電の効率
地熱発電は、地球内部のマグマ熱を利用して水を蒸気化し、その水蒸気でタービンを回転させることで電力を生み出す発電方式です。火力発電や原子力発電と同様に、高温の水蒸気を用いてタービンを駆動しますが、地熱発電で得られる水蒸気の温度は比較的低いため、発電効率は約8%程度と、他の発電方式に比べて低くなっています。
しかしながら、地熱発電では水蒸気の供給が非常に安定しているため、設備の稼働率を高い水準で維持できます。そのため、長期的な運用コストを考慮すると、地熱発電の発電コストは約16.7円/kWhであり、他の発電方法と比較して経済的であるといえます。
まとめ
太陽光発電の効率は、「発電効率」と「変換効率」の2種類に分類されます。「発電効率」は、投入エネルギーのうち電気に変換された割合を示します。一方、「変換効率」は、太陽光パネルが太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換する効率を表します。これらの効率は、様々な要因の影響を受けて変動します。
これらの効率は、太陽光パネルの品質や設置環境など、様々な要因に左右されます。高品質な太陽光パネルの選択と最適な設置環境の整備により、効率を高めることができます。また、日射量、温度、角度などの設置条件にも注意が必要です。効率の維持・向上には、定期的なメンテナンスと発電データの分析も欠かせません。太陽光パネルの汚れ除去や、故障・不具合の早期発見・修理により、効率低下を防ぎましょう。
太陽光発電の運用を成功させるには、効率に影響を与える要因を正しく理解し、効率を高めて発電量を増加させることが重要です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。「オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社」では、太陽光発電所の所有者向けに、太陽光発電のコスト削減と発電効率の向上に役立つ資料を提供しています。本記事よりも実践的で有益な情報を掲載していますので、太陽光発電の収益性を高めたい方はぜひご一読ください。
▼太陽光発電所の所有者向けのおすすめ資料はこちら