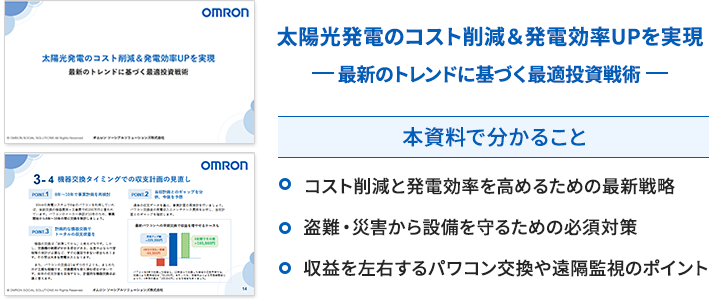太陽光発電で売電するには?売電の始め方から、売電制度、売電収入を増やす方法まで解説

太陽光発電の導入を検討する際、売電についての理解を深めることは非常に重要です。売電とは、太陽光発電で発電した電力を電力会社に販売することを指します。売電収入と自家消費による電気代の節約を合わせた収入が導入・運用コストを上回れば、経済的なメリットが得られていると言えます。
本記事では、売電の仕組みから売電価格、さらには売電収入を増やすための方法まで詳しく解説します。売電収入の増加を目指す方や、太陽光発電の導入を検討中の方は、ぜひこれらの情報を参考に、計画的な判断を行うことをおすすめします。
目次
太陽光発電の仕組み

太陽光発電の基本原理は、太陽光がシリコン半導体に当たることで電気が生み出されることです。このシリコン半導体には、N型とP型の2種類があり、それぞれが太陽光を受けて異なる反応を起こします。N型シリコンでは電子が動き出し、P型シリコンでは正孔が動きます。この2つの動きが組み合わさることで、太陽光パネル全体として電気が流れるようになり、光エネルギーが電気エネルギーに変換されます。
太陽光発電は二酸化炭素を排出しないため、環境に優しい再生可能エネルギーとして知られています。また、太陽光は枯渇せず持続可能であるため、長期的に利用できるエネルギー源として重視されています。今後、太陽光発電技術のさらなる発展と普及により、地球環境の保護と持続可能なエネルギー供給の実現が期待されます。
太陽光発電の種類
太陽光発電は、設置場所と出力容量に基づいて「住宅用」と「産業用」の2つのカテゴリーに分類されます。出力容量は、太陽光パネルとパワーコンディショナー(パワコン)の合計容量によって算出されます。住宅用太陽光発電は、一般的に10kW未満の出力容量を持ち、主に個人の家庭の屋根上に設置されます。このカテゴリーでは、2024年度の売電価格が16円/kWhに設定され、売電期間は10年間となっています。
一方、産業用太陽光発電は、10kW以上の出力容量を有し、広範な土地や商業施設、アパートの屋根などに設置されるのが一般的です。産業用太陽光発電の場合、2024年度の売電価格は以下のように設定されています。売電期間は20年間と、住宅用よりも長期に設定されています。
- 10kW以上50kW未満(地上設置型):10円/kWh
- 10kW以上50kW未満(屋根設置型):12円/kWh
- 50kW以上250kW未満(地上設置型):9.2円/kWh
- 50kW以上250kW未満(屋根設置型):12円/kWh
法律により、太陽光発電の設置者がより多くの利益を得られるよう考慮されており、特に10kW以上の設備では採算性が高くなっています。これは、再生可能エネルギーの普及に向けた優遇規定の一環です。
売電とは?

太陽光発電には、自家消費した後の余剰電力を電力会社へ売却し、収入を得られる売電の仕組みがあります。この制度は2009年に開始され、2012年からはFIT制度(固定価格買取制度)が経済産業省によって導入されました。FIT制度では、太陽光発電で発電した電力を、電力会社が一定期間、国が定めた価格で買い取ることを保証しています。条件次第では、余剰電力だけでなく、発電した電力の全量を売電することも可能です。
また、直接的な収入ではありませんが、太陽光発電により自家消費する電力を自己供給することで、外部からの電力購入量が減少し、電気代の節約にもつながります。つまり、太陽光発電による経済的メリットとして、電気代の削減と売電収入の両方が得られることが挙げられます。売電制度に関する詳細については、この後の章で解説いたします。
太陽光発電に必要な費用と回収期間

太陽光発電の初期費用と投資回収期間は、設置コストと収益性が密接に関連しています。「住宅用」と「産業用」では初期費用が異なり、その差は設置規模や設備の種類によって決まります。2021年の1kWあたりの平均的な設置費用は約25.0万円でした。投資の回収期間は、初期費用をはじめ、発電効率や電力の売却価格に大きく影響を受けるため、慎重な計算が求められます。それでは、「住宅用」と「産業用」のそれぞれのケースについて詳しく見ていきましょう。
住宅用太陽光発電に必要な費用と回収期間
住宅用太陽光発電システムは、一般的に3〜4kWの規模で導入されており、初期費用は約80〜110万円に上ります。この費用には、太陽光パネル代、パワコン代、工事費用、足場組み費用が含まれ、太陽光パネルの枚数によって1kWあたりの単価が異なります。太陽光パネルの枚数が多いほど、1kWあたりの初期費用は低減し、売電収入も増加するため、投資回収期間の短縮が見込めます。
投資回収期間は通常7〜10年ですが、ローンを利用した場合は約2年延長されるのが一般的です。太陽光発電の維持費は、1kWあたり年間約3,000円で、定期点検、パワコンの電気代、太陽光パネルの清掃費用などが含まれます。特に、パワコンは10〜15年ごとの交換が推奨されており、約20万円の交換費用が必要となります。
太陽光パネルの清掃は、発電量が減少した際に行われることが多いですが、太陽光パネルに付着した汚れは発電効率の低下や故障の原因となる可能性があるため、適切なメンテナンスが求められます。
技術の進歩とコスト削減が進む太陽光発電技術は、将来的に更に経済性が向上すると考えられます。住宅用太陽光発電システムへの投資は、長期的な視点で検討することが重要であり、初期費用と回収期間を十分に理解した上で、導入を検討しましょう。
産業用太陽光発電に必要な費用と回収期間
産業用太陽光発電の初期費用は、システム規模に大きく依存します。容量が10kW以上の産業用太陽光発電には、1000kW以上まで様々な規模があるため、「1kW当たり」の相場で考えることが有効です。2021年度の費用相場は、10~50kWで25.5万円/kW、50~250kWで18.3万円/kW、250~500kWで17.2万円/kW、500~1,000kWで17.6万円/kW、1,000kW以上で20.5万円/kWとなっています。
経済産業省のデータによると、2021年の産業用太陽光発電の平均設置費用は25.0万円/kWでした。この費用の主な内訳は、太陽光パネル11.1万円、パワコン3.3万円、架台3.6万円、工事費7.8万円です。一般的な49.5kWの発電所の場合、初期投資は25.0万円 x 49.5 = 1,237万5千円となります。この初期投資は高額ですが、設備規模が大きいほど発電量も多く、FIT制度の期間中に得られる利益により事業の持続が可能になります。
産業用太陽光発電の費用回収期間は通常約10年ですが、資金を全てローンで賄う場合は返済のために約2年程度長くなる可能性があります。また、メンテナンス費用も考慮する必要があります。定期的なシステム点検、監視、サポートに加え、発電効率を保つための除草作業なども含まれます。これらの費用はシステムの規模に応じて異なり、10kWシステムでは約5万円、50kWシステムでは約25万円の年間維持費が目安です。
産業用太陽光発電の導入には、初期費用とメンテナンス費用を理解し、長期的なビジネス計画と資金管理が求められます。
太陽光発電の売電制度

太陽光発電の売電制度は、主にFIT制度とFIP制度(Feed-in Premium制度)の2つに分類されます。FIT制度では、売電価格が固定され、個人住宅所有者と法人が対象となっています。一方、FIP制度は従来、50kW以上の設備のみを対象としており、大規模な発電に適していました。
しかし、2023年度より、一定の要件を満たした10kW以上50kW未満の太陽光発電事業者も、FIP制度を利用できるようになりました。その要件とは、「電気事業法上の発電事業者であること」および「小売電気事業者・登録特定送配電事業者・特定卸供給事業者と直接契約し、発電した電気を供給すること」を満たすことです。これにより、中小規模の発電事業者も市場価格に連動した売電が可能となり、多様な事業者の参入が容易になっています。
FIT制度とFIP制度の主な違いは、FIP制度では売電価格が市場価格に連動し、非化石価値の取引が可能である点です。また、FIT制度では、発電量の予測と実績の不一致(インバランス)に対するペナルティが免除される特例措置がありますが、FIP制度では、計画値と実績値の差が大きい場合、ペナルティが課される可能性があります。
そのため、FIP制度での運用には、高い精度の発電計画が求められます。このように、太陽光発電の売電制度には、FIT制度とFIP制度というそれぞれ特徴のある制度が存在しています。それぞれについて詳しく解説していきます。
FIT制度
FIT制度は、「Feed-in Tariff(固定価格買取制度)」の略称であり、太陽光発電で生み出された電力の買取価格を政府が固定する仕組みです。住宅用の10kW未満の太陽光発電設備では、買取期間が10年間に設定されています。一方、事業者向けの10kW以上50kW未満および50kW以上の産業用太陽光発電設備では、買取期間が20年間に延長されます。
この制度では、発電した電力の買取に必要な資金は、電力消費者から徴収される「再エネ賦課金」を財源として支払われます。これにより、再生可能エネルギーの導入促進が図られています。ただし、売電価格は年々下落傾向にあるため、制度の経済的メリットは減少しつつあると指摘されています。2024年度の売電価格は、住宅用で16円/kWh、事業者向けでは10kW以上50kW未満が10円/kWh、50kW以上250kW未満が9.2円/kWhと設定されています。売電期間終了後は、発電者が電力会社との個別契約を結ぶか、蓄電池を導入して自家消費に切り替えることが期待されています。
FIT制度は、太陽光発電設備への初期投資の回収や将来の収支計画の立案を容易にするために設計された仕組みです。さらに、FIT制度は余剰電力買取制度と全量売電制度の2種類に分類されます。
余剰電力買取制度
余剰電力買取制度は、発電電力の一部を自家消費し、余った電力のみを売電する制度です。この制度は、国がエネルギー利用の効率化を図るために導入した政策となります。利用が必須となるのは、10kW以下の設備と10kW以上50kW未満の設備ですが、2020年以降、10kW以上50kW未満の設備については、30%以上の自家消費と余剰電力のみの売電が求められる条件が追加されました。一方、10kW以下の設備には制約がなく、より自由な売電が可能です。なお、50kWから250kW未満の設備は、余剰電力買取制度か全量売電制度のいずれかを選択できます。
全量売電制度
全量売電制度とは、発電した電力の全量を売電できる仕組みであり、2021年から50kWから250kW未満の設備に限定して適用されています。余剰電力買取制度と比較すると、全量売電が可能なため事業の見通しが立てやすく、太陽光発電を安定した収入源として活用できます。ただし、全量売電制度の利用時には、系統連系工事に伴う高額な負担金が発生するリスクがあるため、注意が必要です。
FIP制度
FIP制度とは、再生可能エネルギーによる発電の売電収入に補助金(プレミアム)を上乗せする制度であり、2022年4月に導入されました。この制度は、再エネの自立化促進と電力市場での自由競争の実現を目的としています。従来のFIT制度では、固定価格での買取費用をまかなうために、すべての電力消費者が再エネ賦課金として負担していましたが、FIP制度では市場価格に基づいた売電収入(参照価格)と補助金(プレミアム)を合算して価格が決定されます。
参照価格は市場価格と連動し、バランシングコストの調整が加えられて決定されます。バランシングコストとは、発電計画値と実績値の差を埋めるための手当であり、2022年度は1kWhあたり1.0円に設定されていました。今後は削減される予定です。参照価格とプレミアムは毎月見直されるため、発電事業者は市場価格変動に対応する必要があります。FIP制度の対象は10kW以上の設備です。10kW〜1,000kWの設備はFIT制度またはFIP制度を選択可能ですが、1,000kW以上の設備はFIT制度を利用できず、FIP制度の利用が必須となります。売電期間はFIT制度と同様に20年間固定されています。
FIP制度は、発電事業者の再エネ導入投資を促進するインセンティブとして注目されています。この制度の導入により、再生可能エネルギーの普及と自立化が進み、電力市場での自由競争が促進されることが期待されています。
FIT制度が終了した後の売電について

FIT制度を利用していたが、固定価格での買取期間が終了したことを「卒FIT」と呼びます。住宅用太陽光発電(10kW未満)は10年、産業用太陽光発電(20kW以上)では20年の買取期間が設定されています。2012年の制度開始から、既に住宅用で卒FITを迎えた方がいらっしゃいます。
卒FIT後は、新たな選択を迫られます。ここでは3つの選択肢を紹介します。なお、卒FIT前から取り組むべき、収益を最大化できる方法については、資料「太陽光発電のコスト削減&発電効率UPを実現 ー最新のトレンドに基づく最適投資戦術ー」をご覧ください。
売電をそのまま継続する
FIT制度の終了後の選択肢として、電力会社が提供する新プランによる売電の継続が可能です。新プランへの切り替えは自動的に行われるため、利用者側で複雑な手続きを行う必要はありません。ただし、新プランにおける売電価格は、FIT制度下と比較して大幅に低く設定されていることが一般的です。そのため、以前と同等の収益を期待することは難しい点に注意が必要です。
新しい電力会社へ売電する
新電力会社への売電先切り替えが可能です。電力自由化に伴い市場に参入した新電力会社の中には、従来の電力会社よりも高い買取価格を提示している企業もあります。ただし、卒FIT後の買取価格は年々下落傾向にあるため、別会社への切り替えを行ったとしても、以前と同等の高収入を得ることは難しいと考えられます。とはいえ、より有利な条件を求めるためには、新電力会社への切り替えや買取価格の見直しを積極的に検討することが重要です。自社に最適な売電先を見つけるために、各社の買取条件を比較し、慎重に選択することが賢明な判断と言えるでしょう。
自家消費に切り替える
電気料金の高騰に伴い、家庭や企業において電気の自家消費が売電収益よりも経済的に有利になりつつあります。その背景には、売電価格の年々の下落傾向と、電気料金の上昇傾向が挙げられます。2024年度のFIT制度における売電単価は1kWhあたり16円である一方、全国平均の電気料金は31円(※全国家庭電気製品公正取引協議会が公表した令和4年7月22日改定の「新電力料金目安単価」に基づく。)に達しています。
自家消費の効果を最大限に高めるには、蓄電池の導入が効果的です。初期投資は必要ですが、国や自治体の補助金制度を活用すれば導入しやすくなり、長期的には電気料金の削減につながります。また、災害時や非常時の電力確保としてBCP(事業継続計画)対策としても有効であり、リスク管理の観点でも優れています。このように、経済性とリスク管理の両面で優位性があることから、売電以外の選択肢として自家消費を検討する価値は高いでしょう。
売電収入を増やす方法

売電収入を増やす方法について詳しく解説します。これらの方法を適切に組み合わせることで、売電収入の最大化が期待できるでしょう。
リパワリング
リパワリングとは、経年劣化した太陽光パネルやパワコンを最新機器に交換する手法です。この設備更新により、太陽光発電所の発電効率が向上し、売電収入の増加が見込まれます。特に運用開始から10年近く経過した設備では、リパワリングによる効果が大きいとされています。これは、技術進歩により太陽光パネルやパワコンの性能が年々向上し、定期的により高効率の製品が市場に投入されているためです。したがって、適切なタイミングでリパワリングを実施することで、投資額以上の収益増加が期待できます。
定期的なメンテナンス
太陽光発電システムにおいて、長期的な安定発電を実現するためには、定期的なメンテナンスが不可欠です。特に、屋外に設置された太陽光パネルは、鳥のフンやホコリ、雨風などの外的要因により、汚れや劣化が進行しやすくなります。放置すると、発電効率が大幅に低下してしまうため、注意が必要です。
太陽光パネルの表面に汚れや落ち葉が付着すると、日光の吸収が妨げられ、発電量が減少します。これは売電収入に直接影響を及ぼすため、定期的な清掃が欠かせません。また、設置場所によっては、火山灰や積雪による発電阻害も考えられるため、周辺環境を考慮した保守点検が重要となります。
高所に設置された太陽光パネルのメンテナンスには危険が伴うため、専門知識と経験を持った業者への依頼が賢明です。専門業者による定期的な清掃や点検により、太陽光パネルの発電量低下を防ぎ、売電収入の安定化が可能となります。太陽光発電システムを長期的かつ効率的に運用し、売電収入を最大化するためには、定期的なメンテナンスを怠らないことが重要です。
設備の最適な設置
同じ太陽光発電設備でも、設置方法の工夫により売電収入の増加が期待できます。特に設置方角と傾斜角度は、発電効率に大きな影響を与える重要な要素です。立地や周辺環境によって理想は異なるため、専門業者にシミュレーションを依頼することをおすすめします。ここでは一般的な状況について解説します。
方角については、最も発電効率が高いのは「南向き」です。南向きの効率を100%とすると、南東・南西は96%、東・西は85%とされています。北向きは更に低く60~65%となるため、設置に不向きといえます。ただし状況によっては、東西2面に太陽光パネルを設置することで、南向き1面と同等の発電量を得られる場合もあります。
傾斜角度に関しては、最適な角度は30度とされ、発電効率は100%に達します。しかし、20度や40度でも98%と、わずかな差しかありません。地域の緯度に応じて、設置角度を調整する必要があります。具体的には、北海道・東北などの北のエリアほど角度を高く、九州・沖縄などの南エリアにいくほど低くする調整が求められます。適切な設置方法を選択することで、売電収入の増加が見込めます。専門家のアドバイスを参考にしながら、最適な設置方法を検討することをおすすめします。
売電に必要な手続き

太陽光発電で売電を始めるには、各地域の電力会社や法律に基づく複数の申請手続きが求められます。本記事では、手続きの中でも重要な事業計画認定申請と系統連系申請について、その手順を解説します。
事業計画認定申請
事業計画認定申請は、FIT制度の下で太陽光発電による売電を行うために、経済産業省へ売電の認可を求める必須の手続きです。この申請により、電力の効率的かつ安全な販売が可能となります。申請の際は、資源エネルギー庁が定める「事業計画策定ガイドライン」に沿って、綿密な事業計画を策定する必要があります。計画が承認されれば、太陽光パネルを含む設備の設置を進めることができます。ただし、ガイドラインに違反があった場合、認定が取り消されるリスクもあるため、内容の入念な確認が重要です。
申請は「再生可能エネルギー電子申請」サイトを通じてオンラインで行うことができます。新規登録後に必要な情報を入力し、必要書類を添付することで完了します。また、FIT制度を利用する場合、設備の設置や運転に関わる費用の報告も求められます。運転開始後は、年に一度の申告が必要であり、定期的な報告を怠るとペナルティが課される可能性があるため、注意が必要です。
最後に、事業計画認定申請は、最新のガイドラインに基づいて行う必要があります。詳細については、経済産業省や資源エネルギー庁の公式サイトで最新情報を確認することをおすすめします。
系統連系申請
系統連系申請とは、太陽光発電設備を送配電事業者の設備と接続するための手続きであり、「接続契約」とも呼ばれています。FIT制度の対象となる設備で発電した電気は、管轄電力会社が買い取る義務を負っており、接続を希望する場合は事業者への申請が必要となります。
通常、電気は電力会社から需要家側へ供給されますが、売電の場合は逆方向に電気を流す必要があるため、「逆潮流」と呼ばれる設備工事が求められます。この工事費用は、申請者である太陽光発電設備所有者が負担しなければならないケースもあります。系統連系申請の流れは、まず申請者が必要書類を揃えて事業者に申請することから始まります。その後、事業者側で技術的な確認が行われ、接続の可否や工事内容が回答されます。接続契約の締結後、実際の工事が進められることになります。
ただし、申請の詳細な手順や必要書類は管轄事業者によって異なるため、それぞれの公式サイトで最新情報を確認することが重要です。円滑に売電を開始するためにも、早めに申請準備を進めておくことが推奨されます。
まとめ
太陽光発電における売電とは、発電した電力を電力会社に販売することで収入を得る仕組みです。事業計画認定申請や系統連系申請などの必要な手続きを経ることで、この仕組みを利用できるようになります。売電により、余剰電力を収益化し、導入コストの回収や利益の獲得が期待できます。
売電制度の代表例としては、FIT制度が挙げられます。FIT制度では、再生可能エネルギーで発電した電力を、国が定めた固定価格で一定期間買い取ります。住宅用と産業用では売電価格や期間が異なるため、制度を正しく理解し、自身の状況に合わせた計画を立てることが重要です。ただし、FIT制度の買取価格は年々下がる傾向にあります。そのため、安定的に収益を伸ばしていくためには、最新の動向や市場トレンドを把握しておく必要があります。具体的な方法としては、リパワリングや定期的なメンテナンス、設備の最適な設置などが効果的です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。「オムロン ソーシアルソリューションズ株式会社」では、太陽光発電所の所有者向けに、太陽光発電のコスト削減と発電効率の向上に役立つ資料を提供しています。本記事よりも実践的で有益な情報を掲載していますので、太陽光発電の収益性を高めたい方はぜひご一読ください。
▼太陽光発電所の所有者向けのおすすめ資料はこちら