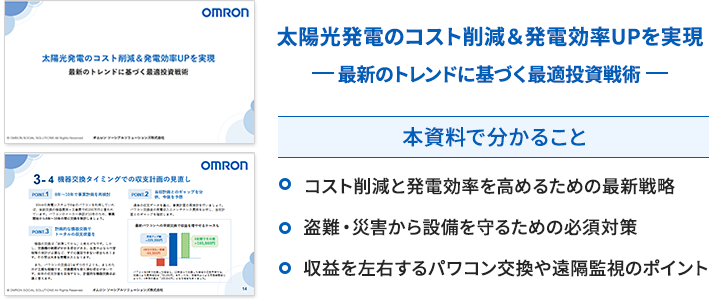太陽光発電の売電価格は?2024年度最新の価格やこれまでの推移、FIT終了後の対策まで解説

太陽光発電の新規FIT認定分の売電価格は年々低下しています。また、FIT制度(固定価格買取制度)による固定買取期間の終了も迫っているため、収益性への不安を感じる方は少なくないでしょう。しかし、同時に太陽光パネルの設置価格も下がっており、自家消費の拡大や、FIT制度を補完する新たな制度が導入されています。
適切な計画と対策を講じることができれば、太陽光発電は現在でも費用対効果の高い投資対象であると言えるでしょう。本記事では、売電価格を取り巻く制度や価格推移、今後の見通しまで詳細に解説します。太陽光発電を最大限に活用するための情報が満載ですので、ぜひご参考ください。
目次
太陽光発電の売電価格とは?

売電価格とは、電力会社が発電事業者から電力を買い取る際の1kWhあたりの電気料金のことを指します。国は再生可能エネルギーの普及推進を目的として、FIT制度を導入しました。この制度により、売電価格が10~20年間保証されるようになっています。(期間終了後は、新電力会社への売電、自家消費が選択肢となります。)
例えば、2024年に設定された10kW未満の設備の太陽光発電の売電単価は、1kWhあたり16円です。この価格に基づいて、10年間にわたり、電気の買取が国によって保証されます。つまり、太陽光発電を導入した発電事業者は、一定期間、安定した収入を得ることが可能となります。
太陽光発電の売電制度

FIT制度とFIP制度の2つが存在します。FIT制度は住宅向けと法人向けの両方を対象としており、買取価格が固定されているのが特徴です。一方、FIP制度は主に50kW以上の設備を持つ法人向けの制度であり、買取価格は市場価格に基づいて変動し、非化石価値の取引が可能となっています。それぞれの制度について詳しく解説します。
FIT制度
FIT制度は、再生可能エネルギー源から発電された電力を、電力会社が一定期間、固定価格で買い取ることを国が保証する制度です。太陽光、水力、風力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギーの普及促進を目的に、2012年に開始されました。
太陽光発電の買取期間は、設置容量によって異なります。住宅用太陽光発電(10kW未満)は10年間、産業用太陽光発電(10kW以上50kW未満および50kW以上)は20年間と定められています。買取価格は、制度開始当初の42円/kWhから年々下がり続けています。
FIT制度の運用において、再エネ賦課金(再生可能エネルギー発電促進賦課金)が重要な役割を果たしています。再エネ賦課金は、すべての電力消費者が電気料金とともに負担する費用であり、電力会社が再生可能エネルギーの買取費用を補填するために使用されます。再エネ賦課金が増加することにより、家庭や企業の経済的負担が増大し、再生可能エネルギー導入に対する一部の不満の要因となる場合があります。
こうした課題への対応として、2022年度からFIP制度がスタートしました。FIP制度では、再生可能エネルギー発電事業者が、市場価格に一定額を上乗せした価格で電力を売ることができます。これにより、再生可能エネルギー発電事業者の収益安定化と、国民負担の抑制が期待されています。
FIP制度
FIP制度は、太陽光発電事業者の売電収入に補助金を上乗せする仕組みです。従来は50kW以上の事業者のみが対象でしたが、2023年度からは一定の要件を満たせば10kW以上50kW未満の事業者も利用可能となりました。
FIP制度の目的は、消費者負担を抑えつつ、再生可能エネルギーの主力電源化と電力市場の自由競争促進を図ることです。この制度によって、太陽光発電事業者は安定的な収入を確保できるようになり、再生可能エネルギーのさらなる普及拡大が見込まれます。
太陽光発電の売電価格の推移

太陽光発電の売電価格は、2012年から2024年にかけて大幅に低下しました。10kW未満のカテゴリでは、2012年度の1kWhあたり42円から2024年度には16円まで下落しています。一方、10kW以上50kW未満のカテゴリでは、2012年度の40円から2024年度の10円(屋根設置型の場合は12円)へと、さらに顕著な減少がみられます。
この売電価格の下落傾向は、太陽光発電技術の進歩とコスト削減、そして市場の成熟化によるものと考えられます。太陽光パネルの効率向上や製造工程の最適化などにより、発電コストが大幅に抑えられたことが背景にあります。また、太陽光発電の普及に伴い、市場競争が激化したことも価格低下に拍車をかけました。
以下の表は、2012年から2024年までのFIT制度における1kWhあたりの売電価格です。
| 年度 | 10kW未満 | 10kW以上50kW未満 |
|---|---|---|
| 2012年度 | 42円(税込) | 40円(税抜) |
| 2013年度 | 38円(税込) | 36円(税抜) |
| 2014年度 | 37円(税込) | 32円(税抜) |
| 2015年度 | 33円(税込) | 29円(税抜) |
| 2016年度 | 31円(税込) | 24円(税抜) |
| 2017年度 | 28円(税込) | 21円(税抜) |
| 2018年度 | 26円(税込) | 18円(税抜) |
| 2019年度 | 24円(税込) | 14円(税抜) |
| 2020年度 | 21円(税込) | 13円(税抜) |
| 2021年度 | 19円(税込) | 12円(税抜) |
| 2022年度 | 17円(税込) | 11円(税抜) |
| 2023年度 | 16円(税込) | 10円(税抜) |
| 2024年度 | 16円(税込) | 10円(税抜) |
出典)資源エネルギー庁|買取価格・期間等(2012年度~2023年度)
この表が示すように、太陽光発電の売電価格は年々下落し続けており、特に10kW以上50kW未満のカテゴリでは、より大きな下落幅を示しています。この価格低下は、太陽光発電の普及を促進し、再生可能エネルギーの主要電源としての地位確立に貢献しました。
太陽光発電の売電価格|2024年度(令和6年度)

2024年度(令和6年度)の太陽光発電システムにおけるFIT売電価格について説明します。住宅用太陽光発電の場合、容量が10kW未満であれば、売電価格は16円/kWh(税込)となります。一方、産業用太陽光発電では、設置形態によって価格が異なります。
地上設置型システムについては、容量が10kW以上50kW未満の場合、売電価格は10円/kWh(税抜)です。50kW以上の場合は、入札制度の対象外であれば9.2円/kWh(税抜)となり、入札制度の適用区分に該当する場合は、入札結果により売電価格が決定されます。屋根設置型の産業用システムでは、容量が10kW以上50kW未満、50kW以上のいずれの場合も、売電価格は12円/kWh(税抜)です。
FIT制度による各年度の買取価格は、前年の3月末またはそれ以前に発表されます。太陽光発電の導入を検討している方は、自身のシステム容量や設置形態に応じた売電価格を確認し、収支計画を立てることが重要です。
2024年度(令和6年度)のFIT制度に関する最新情報

2024年度(令和6年度)において、FIT制度に関して知っておくべき最新情報をお伝えします。
新しい売電価格区分「屋根設置」の新設
2024年度(令和6年度)のFIT制度では、太陽光発電の売電価格が設置場所によって区分されます。特筆すべきは、屋根設置と地上設置で価格が異なる点です。出力10kW以上の産業用設備において、屋根設置は12円/kWh(税抜)、地上設置は9.2円〜10円/kWh(税抜)と設定されました。この改定により、屋根設置の方が地上設置よりも高い売電価格となります。太陽光発電の導入を検討する際は、可能な限り屋根設置を選択することが推奨されます。屋根設置のメリットを活用することで、より高い収益を得られる可能性があります。
FIT制度の動向は、太陽光発電の普及に大きな影響を与えます。2024年度の新たな売電価格区分「屋根設置」の新設は、太陽光発電の導入を検討する上で重要な判断材料となるでしょう。
地上設置型の250kW以上はFIP制度へ統一
2024年度(令和6年度)より、出力250kW以上の地上設置型の産業用太陽光発電は、新設のFIP制度に一本化されます。FIP制度においては、売電価格が参照価格にプレミアムを上乗せした形で決定され、この価格は電力の需給状況に応じて変動します。つまり、電力需要が高まれば売電価格は上昇し、逆に供給過剰時には下落するという仕組みです。したがって、事業者にとっては市場動向を的確に捉え、最適なタイミングで売電することが収益最大化の鍵を握ります。FIP制度への移行に伴い、事業者には今まで以上に市場動向の注視と戦略的な売電が求められるようになるでしょう。
太陽光発電事業の収益を安定して確保するためのポイントについては、『太陽光発電のコスト削減&発電効率UPを実現 最新のトレンドに基づく最適投資戦術』という資料で詳しく解説しています。
売電価格から判断する太陽光発電の費用対効果

太陽光発電の費用対効果を正しく評価するためには、初期投資額、維持管理費、そして売電価格から予想される収益や節約できる電力コストを総合的に判断することが重要です。一般的に、住宅用や産業用の太陽光発電は、10年程度で初期投資を回収できるケースが多いとされています。しかし、FIT制度に基づく売電価格は年々下がる傾向にあるため、将来的な収益性についても考慮する必要があります。
また、設置場所や設備の規模によっても費用対効果は異なります。より詳細なシミュレーションを行いたい場合は、専門家への相談や関連情報の参考が推奨されます。太陽光発電は長期的な投資であるため、慎重な判断が求められます。
売電価格の今後の動向

太陽光発電の売電価格は年々下落傾向にあります。2022年12月に資源エネルギー庁が公表した資料によると、2025年の買取価格目標は、産業用太陽光発電(10kW以上)で7円、住宅用太陽光発電(10kW未満)で卸電力市場価格水準とされていました。しかし、2024年3月に実際に公表された2025年のFIT制度の価格は、産業用が8.9円〜11.5円、住宅用が15円となっていました。つまり、目標値よりはやや高い水準で推移しています。
ただし、導入コストの低下や再エネ賦課金への批判などを背景に、FITによる売電価格の下落傾向は今後も続くと予想されます。太陽光発電事業者は、この売電価格の下落トレンドを見据えながら、事業計画を策定することが重要です。
売電価格の低下に備えた対策

新規FIT認定分の売電価格の低下に備えた対策について解説します。適切な対策を実施することで、売電価格の低下に対応し、太陽光発電設備の採算性を向上させることが求められています。
自家消費量を増やす
近年の売電価格下落を踏まえると、売電収入の追求よりも電気代削減、つまり自家消費量の拡大に注力することが有効でしょう。自家消費量を増やす手段の一つとして、蓄電池の導入が効果的です。蓄電池を活用すれば、日中に発電した電力を夜間や悪天候時にも利用でき、自家消費の促進が可能となります。加えて、法人の場合、蓄電池によるピークシフトやピークカットにより、さらなる電気料金の削減が見込めます。
さらに、完全自家消費システムを採用することで、外部電力供給への依存から脱却し、電気料金高騰や供給不足のリスクを回避できます。ただし、蓄電池導入には初期投資が必要であり、設備の維持管理にも注意が求められます。
補助金の活用
売電価格の低下に備えるには、設置費用の抑制が重要となります。仮に売電価格が下落しても、それ以上に設置費用を抑えられれば、採算性の確保が期待できるためです。その際、補助金の活用により自己負担額を減らすことが可能です。ただし、国の補助金事業では、一部の法人向け事業を除き、太陽光発電単体での支援は限定的です。多くの場合、蓄電池の併設が補助金対象の条件となっています。一方、住宅用太陽光発電については、多くの自治体が独自の補助金を提供しています。お住まいの自治体のホームページで、補助金の詳細を確認することをおすすめします。
リパワリングの実施
太陽光パネルの寿命は通常20年から30年、パワーコンディショナー(パワコン)の寿命は通常10年から15年程度あります。しかし、使用年数が経過するにつれて効率が低下していきます。新規FIT認定分の売電価格が低下していることに加えて、効率低下により発電量が減少すると、売電収入や自家消費量が予想より低くなるリスクが高まります。そこで有効なのがリパワリングです。リパワリングとは、経年劣化した製品を最新の製品に交換する手法であり、太陽光発電の効率を向上させます。技術進歩により、太陽光パネルとパワコンの効率は年々向上しており、市場には高性能な製品が登場しています。設備を更新することで、太陽光発電所の発電量が増加し、売電収入の向上が期待できます。
ただし、リパワリングには費用がかかるため、なるべく安く行えるように努めることが重要です。例えば、複数台のパワコンを利用している場合、まとめて交換することで工事回数を減らし、交換費用の合計を抑えられる可能性があります。このように、リパワリングを適切に実施することで、売電価格の低下に備えた対策として有効に機能すると考えられます。
FIP制度への切り替え
FIT制度からFIP制度への移行は、法人の太陽光発電事業の収益性向上に有効な手段となります。FIP制度では、基本的な売電価格にプレミアムが上乗せされるため、売電収入の増加が期待できます。また、売電価格が市場価格に連動し、毎月見直されることで、需給バランスに応じた収益の最大化が可能です。FIP制度への切り替えにより、売電価格の低下リスクを軽減しつつ、安定的な収益確保が見込まれます。ただし、FIP制度への移行には一定の手続きが必要であり、適切なタイミングでの切り替えが重要となります。
新電力会社への売電
FIT制度終了後の太陽光発電では、新電力会社(PPS)への売電が有効な選択肢となります。新電力会社は顧客獲得のため、大手電力会社よりも高価格での買取プランや独自サービスを提供しています。これにより、売電者にとってより高い収益が期待できます。新電力会社との契約では、最低契約期間の確認が重要です。多くの場合、最低1年間の契約期間が設定されており、短期間での変更は困難です。そのため、事前に各社の買取価格やサービス内容を入念に比較検討することが求められます。
売電先の変更に伴い、購入電力の契約先も同時に変更されるケースが一般的です。購入電力価格の低減幅は、経済的メリットを大きく左右するため、売電条件だけでなく購入条件も慎重に確認する必要があります。電気料金プランの選択では、自家消費量やピーク時の電力使用状況を考慮することが重要です。最適なプランを見つけるには、シミュレーションサイトや比較サイトを活用し、複数のパターンを試すことが有効な手段となります。新電力会社のサービスをいくつかご紹介します。
ENEOS「太陽光買取サービス」
ENEOSの「太陽光買取サービス」は、2019年11月から開始され、FIT満了後の家庭用余剰電力を対象としています。特徴として、電力会社を自由に選べる点にあります。地域ごとの買取価格は、北海道・東北・関東エリアが11円/kWh、中部・関西・北陸・四国・中国エリアが10円/kWh、九州エリアは7.5円/kWhとなっています。また、ENEOSでんきとのセット契約は不要です。
契約期間は1年単位で、違約金なしで解約することが可能です。売電収入は半年ごとに指定口座へ振り込まれます。加入条件は以下の通りです。
- 対象エリアに太陽光発電を設置していること
- 太陽光発電の規模が10kWh未満であること
- 余剰電力買取制度を利用していること
- FIT期間が満了していること
興味をお持ちの方は、公式サイトで最新の情報を確認して、ご検討ください。
ENEOS太陽光買取サービス
丸紅新電力「卒FIT買取サービス」
丸紅新電力の「卒FIT買取サービス」では、「ECOとくプラン」、「SHARPプラン」、「地域応援プラン」の3種類のプランが用意されています。「ECOとくプラン」は標準メニューとして利用可能で、高価買取価格は最高15.0円/kWhと設定されており、地域電力会社と比べて最大約1.5倍の水準となっています。「SHARPプラン」は、期間中にSHARP製の蓄電池を購入すると、売電価格が11円/kWhから15円/kWhにアップする「蓄電池プレミアム」が適用されるのが特徴です。特に、北海道電力管内では他エリアよりも高水準の買取価格が設定されています。
「地域応援プラン」は、余剰電力買取量に応じて10ポイント/kWhが付与されるユニークなプランです。貯まったポイントは全国の返礼品と交換できるため、売電しながら地域を応援することができます。どのプランも契約手数料や解約金はかからず、工事費・契約料も不要です。また、いつでも自由に解約できるため、安心して利用できます。さらに、買取した電力は丸紅新電力が再生可能エネルギー電力として供給するため、環境保全にも貢献できます。
興味をお持ちの方は、公式サイトで最新の情報を確認して、ご検討ください。
卒FIT買取サービス | 個人のお客さま | 丸紅新電力
エネクスライフサービス「太陽光電力買取サービス」
60年以上の実績を誇る伊藤忠エネクスグループの「エネクスライフサービス」が提供する「太陽光電力買取サービス」の特徴は、業界トップクラスの高額買取価格を実現している点です。北海道電力管内では11円/kWh、関東エリアでは2023年10月から2024年3月までの期間限定で14.5円/kWhという破格の条件を提示しています。
契約期間は1年ごとの自動更新ですが、解約はいつでも可能で違約金はかかりません。また、電気の購入先変更は不要で、太陽光電力の買取のみの申込みが可能な手軽さも魅力です。さらに、同社の電力サービス「TERASELでんき」とのセット契約で、買取価格が1円/kWh上乗せされる特典も用意されています。
興味をお持ちの方は、公式サイトで最新の情報を確認して、ご検討ください。
太陽光電力買取サービス
まとめ
太陽光発電の売電価格は年々低下しており、2024年度のFIT制度では、住宅用は1kWhあたり16円、屋根設置の産業用設備は12円、地上設置は9.2円〜10円でした。売電価格の低下が続く中で、自家消費を増やすことは有効な対策の一つと言えるでしょう。FIT制度の終了後は、新電力会社への切り替えにより、より高い収益を得られる可能性があります。
ただし、FIT制度の終了に備えるだけでなく、終了前から取り組むべき施策もあります。例えば、発電所のメンテナンス方法の工夫や運用コストの削減により、現在所有している発電所の残りのFIT期間中の収益を最大化することができます。
太陽光発電のコスト削減と発電効率向上を実現するための最新トレンドや最適な投資戦術については、ホワイトペーパーで詳しく解説しています。本記事よりも実践的で有益な情報が掲載されているため、太陽光発電の収益性向上を目指す方は、ぜひダウンロードしてご一読ください。
▼太陽光発電所の所有者向けのオススメ資料はこちら